概要
慢性閉塞性肺疾患COPDは末梢気道病変と気腫性病変が慢性的に持続することによって、気流閉塞病態が不可逆的となっている疾患である。
COPDに関連する合併症、死亡の割合は増えてきている。予防と診断の過小評価が常に課題となっている。
COPDは軽症であれば自覚症状に乏しい。がこの言い方は必ずしも正確ではない。
では「咳や痰の症状がないCOPDもある」という言い方はどうだろうか。それももちろん正しいだろうが、COPD患者は「なかなか症状を訴えない」という言い方もできると思われる。
この「なかなか」は時間的な意味も量的な意味も心理的な意味もある。
高齢者は「歳だからしょうがない」「タバコがやめられないからそのせいだ」「もうずっとこんなだから」「そんなに辛くない」などと言い、筋力の低下や筋力減少によってまたは意欲の低下などによって、身体活動が低下してもそれが肺の状態に見合い、息切れや辛さが過小評価されていることもある。
患者当人への啓発が、向こうとは言わないが、あまり有効とはいえない病態とも言える。それだけに医師側・医療者側の意識は大切で。医療機関を利用したときこそが疾患認識のチャンスである。
COPDは言うまでもなく喫煙が危険因子である。COPDの呼吸困難は、安静で改善することが特徴である。
慢性咳嗽はCOPDでよくみられる症状であるが、診断の前提ではない。つまりせきが目立たないCOPD患者はいる。
慢性的に痰を喀出することも一般的だが、多量でも膿性でもない。
年数とともに労作時の呼吸困難が悪化していき、やがて低酸素血症となり、呼吸不全となっていく疾患である。
診断
診断までのプロセス
喫煙歴のある50歳以上のものが、肺・気管支あるいは呼吸に関連する症状で医療機関を受診した時が発見のチャンスである。
気管支拡張薬使用後にスパイロメトリーで1秒率が70%未満であることを示ればCOPDと診断できるが、ここで「COPDの診断に気管支拡張薬使用後のスパイロメトリーが必須」としてしまうと、過小評価される。
診断を厳密にすることを要請すると、その分だけ診断が遠のき、そして介入機会も遠のく。このことは特に発言力を持つ呼吸器専門医は認識しておくべきである。
COPDは長期の喫煙歴と呼吸困難があり、咳・痰などの慢性的な症状が併存していて、他の疾患を否定できればかなりの精度で臨床診断できる。
肺機能検査は経過の中で必要であることは間違いないが、介入の前提にしていると、多くの患者が過小評価されたままとなる。
鑑別診断の話になるが、肺の異常影を呈する疾患全般、肺血栓塞栓症、心不全などが否定されたとして、特に気管支喘息かどうかはCOPDの診断上重要ではある。
夜間に増悪するなどの日内変動、春や秋に増悪するなどの季節性の変動、気管支喘息の既往、そもそも労作以外で呼吸困難が増悪するなどの要素があれば、気管支喘息を十分考慮してCOPDの診断に一気に持っていかないようにする。
と言うのは、気管支喘息自体に重要な鑑別疾患が多いからである。
ただし一方でCOPDらしさを収集する努力も必要である。例えば、聴診で呼気が延長している、頸部の呼吸補助筋の肥厚が目立つ、などの身体所見は特徴的である。
痩身であることは多く、鎖骨が目立ちそれを視認しやすい。
肺画像検査も重要で、胸部レントゲン写真で上下に長い肺過膨張所見、CTで気腫性病変が散剤あるいは多発してそれらが融合し、肺野として低吸収領域がみられる・広がっている といった特徴を有する。
これらの情報と除外診断から、(肺機能検査をしなくても)COPDとして介入を始めることは可能である。
ちなみに介入の第一歩は禁煙指導である。
治療・フォローをしていきながら、肺機能検査を実施したり丁寧に循環器疾患を否定していくなどして徐々に確実な診断を目指して詰めていけばいいだろうと思われる。
この時薬物治療を始めその治療反応を確認していくことは診断と治療を兼ねるため、悪くはないマネジメントであると考えられる。
まとめるとCOPDは中年以上で慢性的な呼吸器系の症状を訴える患者全般で考慮する。
検査に対する考え方
診断についてはCTを必須としたい。これは他疾患を否定する、あるいは共存の確認をするだけでなく、気腫そのものを画像的に確認してCOPD病態の可能性を上げるツールとなる。
あとは喫煙歴、身体所見、長期間「何に困っているか」(呼吸困難の具体例、痰の性状、咳の理由など)を確認する。といったことを総合すれば必ずしも肺機能検査がなくとも介入閾値は超える。
すぐに肺機能検査が実施できる診療環境であれば、肺野異常(肺結核や肺炎や気胸)が否定できればすぐ実施し、閉塞性障害の有無を確認する。
専門医との連携はもちろん行って良いし、またそうすべきである。ただしCOPDは患者数が多いため、呼吸器内科医だけでCOPD患者をみていくには限界がある。
よって非専門医もCOPDをみましょう。ではなく「専門医が非専門医に対してハードルを上げない」という点がおそらく重要で、動脈血液ガス分析をしなさい、6分間歩行で評価しなさい、喀痰を分析しなさい、などと言わないことを意識した方がいい。
つまり「(非専門医が)症状に困っているCOPD患者に、吸入薬を試してみる」というところまでは専門医は許容すべきであると考える。
経過と治療
経過
喫煙歴の高かった時代と違い、今はCOPDそのものの生命予後は悪くない。
ただ健康寿命を伸ばすために治療は必要である。
予後不良の因子は想像しやすいものばかりである。
呼吸困難の程度、低酸素の程度、CTでの気腫(低吸収領域)の強さ、広さ、増悪を繰り返すなどがある。
また肺外合併症も予後を悪くする。
心血管疾患、高血圧、糖尿病、低栄養、骨粗鬆症、肺癌、肺高血圧、うつ病などが具体例である。
COPDの末期像は慢性呼吸不全であり在宅酸素療法を必要とする状況、またそれに伴う心不全や肺高血圧症などの循環器系合併症が併発し、全体的に治療・QOL改善に難渋するような臨床状況である。
治療
階段や坂道の歩行で息切れがない段階で、かつ症状がごく軽い場合は特に薬物治療は考えず、禁煙で経過観察する。
禁煙は、もしできたら1秒率が改善する効果がある。「タバコなんて、だめ!」のような規範的な意味で言っているわけではない。
「何か治療をしてほしい」と言ってくるような症状があるか、階段や坂道の歩行で息切れがあるのなら、LAMAかLABAの吸入薬を導入する。
平地で息切れがあるのなら、LAMA/LABAの合剤の吸入薬の適応となる。
吸入ステロイド(ICS)を併用するかは問題になるが、これを考えるには、臨床的にkながえる癖をつける必要がある。気管支喘息を、疾患というより、病態とか要素とか性質などと考えるのである。
COPDと思われる患者にICSを組み込むかは一見悩ましく思えるが、次のように考える。
まずどのCOPDにも喘息の要素があるかもしれないと考えておくと良い。COPD評価の段階で気管支喘息を意識して進めることになるはずだが、この段階というのは「喘息が明らかにあるかどうか」という評価となる。
このとき、「明らかにあるとはいえない」は、気管支喘息病態の尊大の否定にならないことを心得ておく。
私の眼目は「喘息を厳密に否定しなさい」ではなく、「否定できないままCOPDの介入を始めて良い」である。気管支喘息を否定することは難しい。
LAMA単独で始めるにせよ、LAMA/LABAで始めるにせよ、うまくいかなかったらICSを足せばいいのである。
それなりに鑑別を進めた上でCOPDと診断したはずなのに、LAMA単独で症状の改善が今ひとつで、ICS/LABAに変更したらすっかり改善したということも実臨床では経験される。
このように、どれを選ぶか?と構えると薬剤を正確に一つに絞りたくなるが、そうではなく、色々移行できると良い。よって製剤選択の観点としては「会社」「吸入器の種類」など統一する・揃えることを重視すると良いかもしれない。
例えば「ドライパウダー定量吸入器でエリプタ」などのように決めてしまえば操作/吸入法は薬剤の内容によらず一緒であるから、エンクラッセ(LAMA)、アノーロ(LAMA/LABA)、レルベア(ICS/LABA)、テリルジー(ICS/LAMA/LABA)などを相互に使い分けすれば良い。
初めから同じ薬剤を一生使うことを決断したり、症状の効果だけを見たりせず、吸入のしやすささ・継続性などを重視してみせる。
なお抗コリン薬の禁忌に該当していないかは、導入前に必ず査定する。有症状かつ未治療の前立腺肥大、閉塞隅角緑内障の既往、重度の心疾患、機能性の腸閉塞のハイリスク患者などでは、抗コリン薬の導入は一旦見合わせる。
逆に、病名・既往だけで禁忌とみなさないことも必要である。例えばよく管理された前立腺肥大、開放隅角であり、眼圧が少し高いことだけを観察あるいは点眼治療されているなど、抗コリン薬が禁忌とまではいえないものもある。泌尿器科や眼科医に一度診てもらうようにする。
フォロー
よくならない時にアクションを変えることは重要である。
ICSを入れてみるアイデアのほかに、肺以外の循環器疾患疾患の再評価・鑑別を改めて行う、吸入がうまくできているかを確認する、などを検討してみると良い。
心エコーで心機能を見たり、肺血栓塞栓症がないかをみるためにD-dimerの測定・造影CT・肺血流シンチグラフィなど行ったりすべきである。
また吸入手技の技術確認は、薬剤師、看護師でも可能であり、すでによく確認されている場合もあるが、担当医も気にしておくことが大事である。
一番簡単な方法は、処方した吸入器を診察室に持参してもらって、その場で目の前で吸入してもらうことである。そこに家族か看護師などが立ち合えば、なお良い。
よくなりきらないことの一番の要因は、吸入継続のアドヒアランスである気がしているが、そのほかに、吸入時の吸入の手応えがなく、「吸入できた気がしない」などという治療に関する小さな後ろ向きの心理の積み重ねがあると個人的には思っている。
「それで吸入できているんですよ」と他者が励ますことが肝要である。長い治療になるのだから励ますのは当然である。
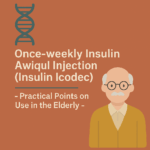

コメントを残す