概要
胸腔内に空気が蓄積している状態を気胸という。
自然気胸(原発性と続発性)、外傷性気胸、医原性気胸がある。
自然気胸の原発性と続発性は既知の肺疾患があるかどうか、医原性も機序はほぼ外傷性で、胸腔穿刺・経皮肺生検、胸膜生検、鎖骨下あるいは内頸静脈カテーテル留置、経気管支肺生検/気管支鏡手技、人工呼吸器の陽圧喚気などに関連したものが挙げられる。
緊張性気胸は、静止している診断名というより動的な病態であり、急な空気の圧迫により静脈圧を超えてしまい、急激に静脈の環流不全が生じて起こる。
原発性の自然気胸は、背が高く痩せているものに多く、45歳未満の若年男性に多い。
喫煙はリスクになる。
続発性気胸は、肺疾患の存在が原則で、状況からごく当たり前に気胸が想起できる病態が多い。
具体的には、COPD、間質性肺炎、気管支喘息、結核に罹患した肺、肺炎、嚢胞性肺疾患などである。
肺疾患を想起させない病態では、月経随伴性の気胸(子宮内膜症の一型)、Marfan症候群やEhlers-Danlos症候群などの結合織疾患などがある。
疑い方 診断までの経緯
胸痛と呼吸困難の二つが、それぞれに程度の大小はあるが、必発である。
胸痛(側胸部痛など)がメインになることが多い。呼吸困難は多いが、主訴になることは少ない。
咳が誘発されることも珍しくない。
胸痛は通常いわゆる胸膜痛で、深呼吸で局所的な疼痛が誘発される性質である。
肺疾患を持っているとわかっていれば当然であるが、原発性自然気胸になりやすい患者背景として「若年」があるので、結局は既往歴によらず胸部レントゲンを実施することになる。
胸部レントゲンの実施を厭わないことが重要である。
何かと言い訳(酸素飽和度が保たれている、呼吸困難がない、背が高くない、女性、胸部聴診で呼吸音が聴こえて問題がない、血液検査の結果を待ってから〜、など)をして画像けんさを端折ると見逃す。
局所的な胸郭の疼痛を訴えた患者、胸膜痛と思えた患者、「酸素飽和度の低下+胸痛」を訴えた患者、など胸部画像検査の閾値を日頃から低めに持っておく。
気胸と思えた全員に、バイタルサインや一般状態(応答や活気、意識レベルなど)を確認する。
この時点で現実的な鑑別疾患は、肋骨骨折、肺炎・胸膜炎、肺癌などである。
胸部レントゲンは、虚脱の程度を決めるのに肺尖が鎖骨レベルかそれより下がっているかが目安になるので、まずは疼痛側の肺尖部の含気を見る。
一般に含気がない部分は、「肺野(実際には肺ではない)」が綺麗で明るい印象の黒色になる。
理屈よりも初見時の画像の見た目の印象を重視していい。
含気がない領域は、肺紋理が消失する。ざらつきが消えトーンが均一になる。日頃から、肺血管を目で追っておくと読みやすくなる。
肺の虚脱の程度は胸部単純X線写真で判断するが、日本気胸・嚢胞性肺炎疾患学会は、癒着がない場合には3段階に分類している。
軽度:配線が鎖骨レベルまたはそれより頭側にある。またはこれに準ずる程度。
中等度:軽度と高度の中間程度
重度:全虚脱またはこれに近いもの
軽度と中等度の差は、肺尖部の虚脱の場合に鎖骨より上にとどまれば軽度と判定できる。
肺尖部が鎖骨より下にまで落ちていれば中等度とする目安となる。
背臥位で撮影した単純写真の場合の気胸を見抜く読影は、多少技芸というかアートな側面もなくはなく、立位が取れずに気胸か迷う場面ではCTを行う。
CTは気胸の有無が一目瞭然のところがあり、単純写真の読影に迷う場合は実施する。
経過と治療
経過
自然気胸患者が、経過観察あるいは胸腔ドレーン留置によって治療された場合、30%は再発する。
外科的治療がなされた場合の再発は少ない。
自分自身で再発を心配して受診する事が多いが、その自己診断の正診率はそれほど高くないように思える。
しかし再発がありうる以上、再評価せざるを得ない。
治療
虚脱が軽度で症状が乏しければ経過観察とする。
中等度以上であれば、胸腔ドレナージが望ましい。
画像検査時に軽度に思えても、体動で呼吸困難があったり酸素飽和度が低かったりする場合や症状が短時間で増悪傾向にある場合にも、胸腔ドレナージが必要であるとされる事が多い。
個別に、呼吸器外科医(あるいは呼吸器内科医)と協議して治療法を検討するが、経過観察、胸腔ドレナージ、胸膜癒着術、気管支鏡下気管支塞栓術、胸腔鏡下手術から選択される。

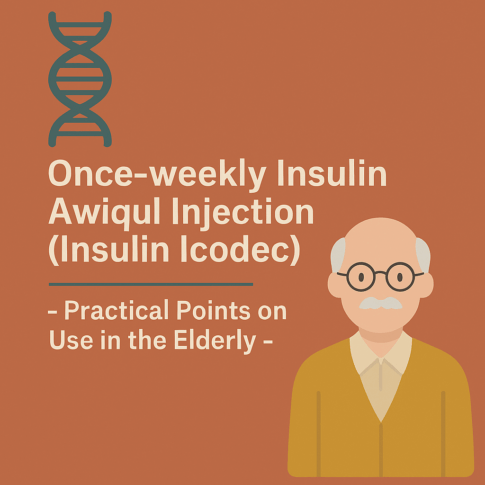
コメントを残す