概要
がん死亡数の推計では、肺がんは、2021年にはいつも争っている大腸がんを上回り1位に返り咲いた。年間死亡数も7万5000人を超えている。
また2012年の段階ではあるが、日本人の調査で肺がん患者のおよそ3/4が75歳以上であるとされ、高齢化が進んでいる現状がある。他方、高齢であっても予後が飛躍的に改善してきている現状もある。
その背景として、単一遺伝子の変異によって癌化するドライバー遺伝子(EGFR、ALK、ROS1、BRAFほか)の同定とそれに対応する治療薬(チロシンキナーゼ阻害薬:tyrosine kinase inhibitor:TKIなどの分子標的薬)、そして免疫チェックポイント阻害薬、これらの高い有効性がある。
QOLが良ければいいという目標を超えて、生存期間も延長するような成績を残せるようになりつつある。
つまり、「高齢の肺癌」を診たときに、ただちに「生存を諦める」様な時代ではなくなった。意識改革が必要である。
肺癌の診断の中心は、今でも画像検査である。
一次検査(一次読影)で用いられるのは胸部単純X線写真だが、これも今やデジタル画像が普及し、読影者の任意で拡大、濃度・コントラスト調整などができ、比較読影の労も少ない。
さらには今後、一次読影にAI診断が普及すれば、医師はその診断の確認あるいは二次読影に業務がシフトできる。
肺癌の発生には、患者自身の癌発生の素因や喫煙感受性などの他、気道の慢性炎症が密接に関連しているとされる。
具体的には、喫煙、加齢、COPD、肺線維症(その素地・前段階である間質性肺炎)、気腫合併肺線維症(combined pulmonary fibrosis and emphysema:CPFE)などが有力である。
COPDなど、背景となる肺にダメージや嚢胞がしっかりある場合には、肺癌でも典型的な結節影とならないことに注意する。嚢胞壁に沿って進展する場合もある。蜂巣肺でも同様である。
こうした高リスクの群には禁煙を勧め、COPDや間質性肺炎であればその治療を行う。そして、腫瘍マーカー(CEA、シフラ、proGRP)測定と胸部CTを年1回行う。
CT画像 診断までの経緯
肺癌では、いわゆる成書ではその症状として咳や血痰などを呈するなどと記述されるが、症状があれば日本の診療では(患者自身も望みがちだということもあり)すぐに画像検査に至りやすい。
そのため、肺癌を疑う結節影などは、肺癌を症状から疑って撮った画像からではなく別の理由で撮ったもので偶然見つかることが多いだろう。
胸部単純写真でもCTでも、肺野を大きく占めるような腫瘤を指摘できた際も、当たり前だが精査に結びつけやすい。
臨床医にとって問題であって、判断が要求されるのは、ほぼ無症状で見つかった肺内病変に対するマネジメントである。その中で最も重要で大きな要素が「CT画像の読影」である。
ここでは結節影のCT読影について(特に末梢病変を意識して)簡単に述べる。「5〜30mmくらいの円形っぽいもの」を結節と呼ぶことにする。
まず結節の辺縁の性状を見極める。平滑、分葉状、spicula、halo(辺縁がすりガラス状影)などがある。
平滑
教会が明瞭な辺縁を持つ結節の多くは寮生で、良性腫瘍の場合は周囲組織を壊さずに無症状で発育するので綺麗な円形となり、また大きくなる(大きくなるまで気づかれないから)
ただし、状況から転移性肺腫瘍(肺転移)を疑っている時や、それもあり得るような時は、多発性で境界明瞭で辺縁平滑な結節影でも良性とみなさないようにする。
他方、辺縁がギザギザ、トゲトゲ、分葉状、haloなどは悪性が示唆される。
境界明瞭でも辺縁が不整(ギザギザ)なら腺癌があり得るので、明瞭だからと悪性を否定しない。
分葉状
分葉状、つまり辺縁がぱっと見凹凸があるようなパターンは、多くの肺癌でみられる。特に喫煙者でこのことに注意する。
Spicula
肺癌の有名な所見の一つで重要だが、完全な特異性があるわけではないのでこだわりすぎないようにする。
Spiculaは結節辺縁に見られる1mm以上の刺状の構造物をいう。
halo
結節辺縁にすりガラス影があるパターンである。この時結節自体の辺縁が境界明瞭である場合、これは肺胞上皮置換型の腺癌の所見として特異的であるとされる。
結節内部
次に結節の辺縁ではなく内部の性状についてであるが、基本的に癌では細胞密度が高く、これはCTでは縦隔条件での結節影の明瞭性で示唆される。
肺野条件で「結節らしき」ものを見たら同じ部位を縦隔条件でも確認すべきである。縦隔条件でもしっかり同程度の大きさと「濃度」で結節影を認めたら、肺癌を十分疑っておく。
ただし結節内部にエアブロンコグラムがある場合も肺癌であることがある。分化度の高い腺癌などでは、気管支を破壊せず(緩徐に)発育する。
すりガラス影のみの結節でも肺がんのことがある。
特に、すぐに消えず長時間存在し続けるすりガラス状結節は、上皮内癌であることがある。
結節辺縁の所見として胸膜陥入像が有名だが、肺癌として高い特異性があるわけではないのでこだわらない。
結節周囲に、気道に沿った、つまり小葉中心性の散布巣を伴う時は肺癌の可能性は低い。結核や非定型型抗酸菌症など炎症性のものの可能性が高い。
フォロー
結節の大きさが小さいなど曖昧な所見であった場合は、間隔を空けてCTを行い、経時的変化をみる。
例えば肺腺癌の体積倍化時間は約161日という報告がある。
しかし組織型や背景肺のパターンによっても異なる。
一番発育が遅いであろう、すりガラス結節パターンの腺癌では1000日を超えることもある。
高分化型腺癌でも、無症状のまま倍化し、それに約1年要することもある。
COPD(あるいは肺気腫)や間質性肺炎(あるいは肺線維症)では思ったよりも発育速度が速いことがあるため、こうした背景肺を持っている場合は、初めは1〜2ヶ月ほどでフォローをした方がいいだろう。
増殖が遅いであろう結節病変では、初回は3ヶ月後くらいのフォローが現実的だと思われる。
フォロー時に大きさなどの変化がない、あるいは乏しければ、間隔をもっと空けても良いだろうが、迷うくらいなら専門家に紹介した方がいい。
確定診断
確定診断は生検で行うが、気管支鏡検査で近年進歩が見られる。
特に、超音波を併用したものが重要であり、ガイドシース併用超音波内視鏡検査(EBUS-GS)と超音波気管支鏡ガイド下針生検(EBUS-TBNA)がある。
EBUS-GSは、末梢の小さな病変でも診断精度が高い。また、繰り返しの生検が可能である。
EBUS-TBNAは、気管支に接する肺門や縦隔リンパ節病変に対してもリアルタイムに可視化して生検できる。
治療
小細胞癌は、早期に勢いよく転移するので、偶然発見されたようなStageⅠ病変だけが手術療法が考慮される。
限局型であれば、化学療法だけでなく、放射線療法を併用する。
進展型は延命を目指して化学療法となる。高齢でも、化学療法の反応は良いので、延命や緩和を目的として化学療法を行うこともある。
非小細胞癌ではStageⅢAまでは手術を検討できる。もちろん病期に応じて放射線治療や化学療法を併用する。
切除不能(転移再発含む)非小細胞癌で、大きな治療の進歩が見られている。
まず扁平上皮癌か非扁平上皮癌かに分類する。PD-L1の発現を検索し、発現量を調べておく。
EGFR遺伝子変異などのドライバー遺伝子変異の有無を検索する。
腺癌では、EGFR、ALK、ROS1などが陽性ならそれぞれに対応するチロシンキナーゼ阻害薬を使用できる。
ドライバー遺伝子変異陰性でも、PD-L1が高発現(5%以上)なら免疫チェックポイント阻害薬の適応となる。
扁平上皮癌でも、やはりPD-L1が高発現なら免疫チェックポイント阻害薬が使用できる。
ドライバー遺伝子変異陰性で、PD-L1が低発現(50%未満)であれば、細胞傷害性の抗がん剤は少なくとも使用せざるを得ない。

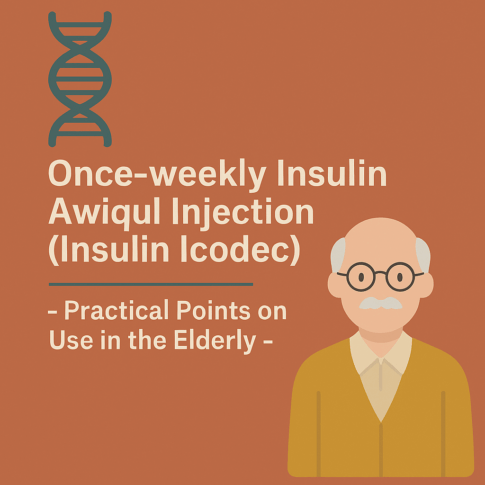
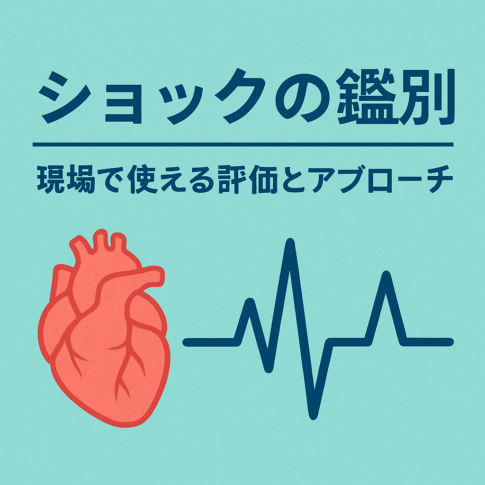
コメントを残す