過敏性肺臓炎の概要
過敏性肺炎は、アレルギー機序で生じる間質性肺炎の一つである。
環境中の特定の抗原を反復して吸入することで感作が成立した後、再度その公言を吸入することで、その抗原と特異抗体あるいは感作リンパ球が肺の局所で反応し、その結果病変が形成される。これが画像的に肺臓炎として表現される。
特異抗体がⅢ型アレルギーで、感作リンパ球がⅣ型アレルギーである。
過敏性肺炎は、臨床像から急性と慢性に分類される。
慢性過敏性肺炎は、線維性間質性肺炎に分類され、特発性肺線維症や膠原病肺かもしれないと思われて診断されることが多い。
急性過敏性肺炎は、肉芽種を形成するので肉芽種性肺疾患と分類される。肉芽種というと慢性的に固着化した病態のイメージを抱くが、実査には抗原回避のみで改善する一過性の病態であることが多く、「肉芽種」を意識して診療することは少ない。
急性では具体的には抗原暴露4〜6時間ほどで発熱、胸痛、咳、呼吸困難が現れ、さらには胸部異常影を呈する。
過敏性肺炎は吸入抗原の種類、量などによって病像が異なってくるとも言える。よって相当軽い症例も考える。
例えば、症状は微熱や倦怠感程度で、念の為採血をしてみたらCRPが少し上がっており、CTでは小さなすりガラス影があった、のようなケースは時々遭遇する。
もちろん証明は困難だが、吸入した抗原の質と量によってはあり得るだろう。
日本では、慢性過敏性肺炎は鳥関連過敏性肺炎が多く(真菌が原因となる夏型や住居関連は少ない)、急性は夏型過敏性肺炎が多い。
全体の頻度は、鳥関連が最も多い。続いて農夫肺、夏型過敏性肺炎、住居関連と続く。
鳥関連の過敏性肺炎(多くは慢性型)では、鳥の糞や羽毛に含まれる抗原が原因となり、鳥を飼っている人や業者に発症するいわゆる鳥飼病おこれに含む。
製品化されたもの、例えば羽毛布団や衣類によるものも含まれる。
農夫肺は牧草に存在する放射菌が、夏型ではトリコスポロンアサヒが原因となるという対応が一般的である。トリコスポロンアサヒは高温多湿の気候、古い木造家屋に増殖する真菌の一つである。住居の様子を聴取することが診断上重要になる。
加湿器肺、あるいは羽毛製品による鳥関連過敏性肺炎では、夏型と違って冬季に発症・増悪する。
きのこ栽培者肺など、職業暴露に関連するものも多く、職業歴の聴取は重要である。
加湿器肺のように、家庭内での暴露による発症もありうるので聞くべきは職業がらみだけに限らない。
疑い方
先に言ってしまうと、本症は抗原暴露歴がわかってもわからなくても、結局は気管支肺胞洗浄液による検討、詳細な環境調査、環境誘発試験あるいは抗原吸入誘発試験など、診断確定に線のmんてきな技術と知識を要する。
よって、非専門医・一般医は本症を疑うところまでが守備範囲である。
抗原を特定する重要なプロセスでは、そうした環境誘発試験あるいは抗原吸入誘発試験に至る前の段階では病歴聴取なのであり、それならば非専門医でもできそうな気がしてしまうが現実にはそうは甘くない。
かなり微に入り細を穿つような詳細な病歴聴取が必要であり、専門医以外には少し難題である。
ただ、基本的には、職業・職場環境・自宅や自宅周囲環境・趣味といったところを軸にして聴取することになる。
血液検査では、夏型の抗原になりうるトリコスポロンアサヒ抗体、そして鳥特異的抗体くらいしか容易に特異的な検査ができない。
疑って紹介、というのが実際的なステップとなる。
急性過敏性肺炎は「肺炎を反復するうちに、それが感染症とは思えなくなってきた」というような状況で疑う。
ワン・エピソードだけで特異的な診断に至らせることはおそらく困難である。
ただ発熱、胸痛、咳、呼吸困難が急性経過で現れるため、肺画像検査に自然に至りやすい。
胸部単純写真では、両側の淡い透過性低下像に終わることが多い。つまりCTが必要である。
CTでは、すりガラス影、小葉中心性粒状影などを呈する。
ここまでの経過で環境暴露の可能性を想起できるかが鍵となるが、現実的にはそのような問診がルーティンに行われることはほぼなく、「治りが早い」「短期間で繰り返す」といった、いつもの肺炎との差異でやはり気づかれる。
抗原の心当たりがつきやすいならば、再曝露での臨床像の再現、回避での改善などで診断が確かとなりやすい。
慢性過敏性肺炎では、そう診断される前にほぼ前例で「間質性肺炎だろう」とされて呼吸器内科に相談されることになる。
間質性肺炎との遭遇は一般医でもそこまで稀な事象でもないため、間質性肺炎の原因鑑別として慢性過敏性肺炎の可能性を入れておくということで良いだろうと思われる。
低くてもそこまで詰めることができれば、その時点で初めて「鳥関連」の問診を追加すれば良い。
鳥を飼っているか、だけでは足りない。羽毛布団・羽毛枕・ダウンジャケットの使用の有無、家庭の羽毛製品(ハタキなど)の有無、鳥の剥製の有無、鶏糞肥料を使うような園芸をしていないか(自分でしていなくても周りでされていないか)などまで聴取する。
鳥自体との接触歴はもっと聴くことになる。患者自身ではなく近隣の人が飼育していないか、鳥小屋や鳥の巣はないか、今ではなくかつて鳥を飼っていなかったか、飼っているなら何を何匹くらい飼っていたか、庭や近くの公園や神社に鳥が飛来してこないか、餌付けしているような人はいないかなどとにかく細かく聴く必要がある。
慢性過敏性肺炎の診断は、通常は外科的な肺生検が必要になる。
経過と治療
経過
急性の予後は良い。
慢性では繊維化を伴っていると進行性であり5年生存率50〜70%ほどである。
治療
急性で軽症であると、抗原回避だけで改善する。
急性でも呼吸不全を伴うような症例ではステロイド使用が行われる。
プレドニゾロン20〜40mg/dayなどから始め4週程度使用、重症と思えば40~60mg/dayなどから始め4週程度使用する、というようなことがされるがこれが正しいかはわからない。
慢性では、0.5mg/kg/dayほどの中等量とシクロスポリンを使用し3ヶ月以上治療するやり方がとられるようだが、これでいいのかはわからない。
繊維化を呈している例では、抗繊維化薬は良さそうである。

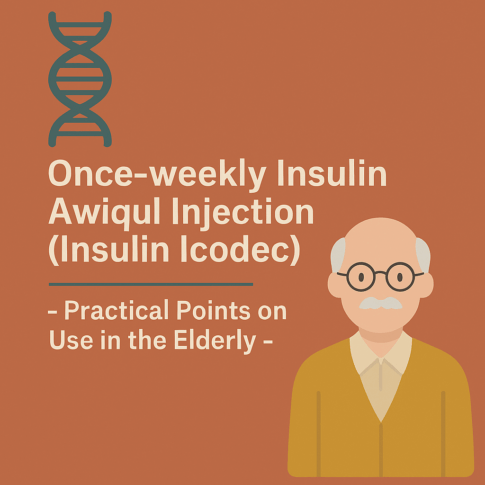
コメントを残す