まず間質性肺炎(interstitial pneumoniae:IP)というのは、それ自体広い概念であるが、これすらも「びまん性肺疾患」という大きな総称に包含される概念である。
びまん性肺疾患に含まれるものは、①特発性のIP②膠原病③腫瘍④感染症⑤外因性などのほか、である。
びまん性肺疾患に含まれる核病態の多くが、間質を病変の取材にしているため、画像だけで各々の病態同士を区別することは難しい。
画像・病理組織から入ると(臨床医は)錯綜する。そうではなく、「IPの原因は何か」という切り口で考えると途端にスッキリしてくる。
その「原因」の検討は、通常「情報収集」によって行われる。すなわち、病歴、基礎疾患、性別、服薬歴、血液検査の結果などである。何より、これは一般内科医にも十分可能である。
例えば関節リウマチの患者にIPを見たら、その原因は関節リウマチらしいとわかる。
また例えば、(黄芩入りの)漢方薬を服用している患者にIPを見たら、その原因は漢方薬らしいとわかる。
本来はIPは病理組織によって定義される。しかし実際には、ある程度の画像パターンと臨床情報収集によって、臨床的に診断あるいは推定することができる。
悪性腫瘍や増殖性疾患については、推定はできるが、確定診断は病理組織でなされる。
非定型肺炎やウイルス性肺炎、ニューモシスチス肺炎、粟粒結核などは、概念上は美慢性肺疾患に含まれてしまうが、画像的にIP初見を部分的に呈したとしても、IPとしての軸ではなく病原体側の要素で診断されるだろう(どの原因微生物であるかが重要であって、画像のパターンは定義・分類に与らない。)
過敏性肺臓炎も、各種抗原に対する反応病態であって、何に反応しているかで分類される病態となる。
臨床家は「IP」と聞いたときにそれが画像パターンのことを指しているのか、それとも臨床診断名を指しているのか、少し意識すると良い。
画像パターンを指す場合はかなり多彩な病態を含む概念となるが、臨床情報と画像で臨床診断したものを(ほぼ慣用語として)「IP」と呼んでいる現状があると思う。
この文脈における「IP」について取り組むフェーズが臨床には必ずあり、次にその時のことを考える。
この「IP」をあえて言い換えれば、「分類前のびまん性肺疾患のうち、画像所見ですぐにIPがあるとわかるもの」となる。
すると、もしリウマチ・膠原病の診断がまだついていない段階で考えるのだとすると、このIPを特発性(idiopathic IP:IIP)と膠原病肺の2群に分けると実際的である。
画像所見ですぐにIPがあると分かれば、さらに見通しをつけやすくなる。
リウマチ・膠原病があるかどうかは、IPらしいとわかった後に血清検査などで比較的容易に推定できる。
具体的には「IPらしい」→「リウマチ・膠原病を血液検査で精査」→「陽性ならその当該疾患、陰性ならIIPかもしれないと考える」という手順である。
臨床でもよく使われる用語の、UIP(usual IP)、 NSIP(nonspecific IP)、COP(cryptogenic organizing pneumoniae:特発性気質化肺炎)、DAD(diffuse alveolar damage)といった名称は、実際には病理組織名である。
これには対応する臨床名であって、それぞれIPF(idiopathic pulmonary fibrosis:特発性肺線維症)、NISP、OP、AIP(Acute IP)などと称されるが、臨床現場では「通じれば良い」という考えである。
Contents
IPの画像
UIPとNSIP
IIPの大部分はUIPとNSIPである。
両側性の間質陰影が、下葉優位に見られることが特徴である。
そしてそれは初期は背部に生じ(ちなみに初期から背側にFine Cracklesを聴取するので聴診も重要である)進行して下葉全体、さらに進めば上葉まで達するという経過になる。
UIPとNSIPの区別は、UIPではさまざまな段階の病変が混在するが、NSIPは均一である。という目安でなされる。ただ、CT上の「蜂巣肺」は、進行したUIP(つまりはIPF)の圧倒的な特徴であり、区別が捗る。
間質病変が淡いか微細な時、CTではこれをいわゆるGGO(Ground glass opacity)という所見で表現される。これはIPの特徴ではあるが、UIPかNSIPかを区別するものではない。
NSIPはcellular NSIPとFibrotic NSIPに分けられる。
Cellular NSIP
進行が早く、肺胞内にも浸潤し活動性が高い傾向があり、胸水を伴うこともあるのがCellular IPである。疾患単位を指すというよりそういうフェーズ、あるいは治療反応から病態を推測する際に用いる用語といっていい。
抗炎症、免疫抑制治療に反応するタイプともいえる。
Fibrotic NSIP
Fibrotic NSIPはIPFという臨床病態のうちの一つの病型(実際には病理名)と考えるとわかりやすい。なおIPFのうち多くを占めるのはUIPである。
慢性UIPは、通常間質の線維化と程度によって肺胞構造の破壊の所見が見られるので特定しやすい。
CT上、線維化によって気管支は牽引されて気管支径が拡大する。もちろんUIPだけの初見ではなく、Fibrotic stateなNSIPでも見られる。
蜂巣肺は述べたようにIPFのhallmarkであり、肺底部・背側優位である。また、繊維化が強いと肺底部のfibroticな構造変化を反映して横隔膜が居城し拘束性障害につながる。この画像所見は特徴的である。
OP(COP)
OP (COP)は、UIP/NSIPとは区別しやすい。
IPの一型と認識していると間違える。OPは浸潤影が目立つので臨床では細菌性肺炎に間違えられる。
OPは、やや下肺野優位で、末梢胸膜直下に接した病変を含む、浸潤影主体の多発病変とその周囲すりガラス影が見られることが特徴である。
一人の患者の中で、ある時点において同時に様々な所見が混在している肺を見たら疑う。
OPで見られる大きな浸潤陰影は、細菌性の大葉性肺炎と見紛うもので、気管支透亮像も伴う(むしろ、細菌性のそれより綺麗に見える)
OPでは結節影、胸水などもありうる。
経過で自然消退・心病変出現を繰り返すことがあり、陰影が移動して見えることもある。むしろこれはOPの特徴である。
ざっくりまとめれば、肺CTでコンソリデーション(CT上でべったりと真っ白で均一な陰影を指し、陰影内の肺血管が全然見えない初見を指す言葉)が多発しており、GGOなど他の所見も伴う場合にOPを考えるのである。
臨床的には、関節リウマチやシェーグレン症候群の患者に生じることが多く、これらの患者であるともともとわかっていればそれもかなり有益な情報となる。
少し脱線するが、シェーグレン症候群はIP合併が多いわけではなく、多いのは関節リウマチ、強皮症、多発性筋炎、皮膚筋炎、混合性結合組織病である。
顕微鏡的多発血管炎は血管炎であるが肺に罹患することもあり、その時の肺画像はIPパターンとなる。
膠原病肺
IPを認識したあと、そこからどの膠原病があるのか(あるいは潜在するのか)を推定するにあたり、画像パターンや病理組織から区別しようとするのは実際的ではない。
その理由の一つは、肺生検をしたとしてもIIPか膠原病によるIPかの区別ができないからである。
肺生検が無駄というわけでは決してない。血管炎やリンパ腫が判明することもあるだろう。
もう一つの理由は、膠原病としての所見・膠原病と診断できるだけの病状がない状態では、理屈上IIPと膠原病IPと区別はできないことになるが、そもそもIPに対する基礎疾患による治療方針の違いがないからである。
また、病理組織所見の違いが治療方針に左右することもほとんどない。
というのも治療適応や治療内容は肺病態の進行の速さで決まり、特に急性期は内容は大体同じであるので、組織の違いで臨床対応の大きな違いを生まない。
実際的な話をすれば、血清の陽性だけ判明し(例えばリウマチ因子、抗CCP抗体、抗ARS抗体、抗MDA-5抗体、MPO -ANCAなど)、肺野が先行した膠原病病態であると推定できることがある。
この時個々の膠原病に対応した治療がなされることが多いものの、急性期の進行の速さが重要であって、つまりは速いなら「ステロイド大量(±パルス)+免疫抑制薬1〜2剤」という初期対応は共通している。
IP(だけ)を認識した時にこなう検査
肺機能検査や血液ガス分析
CRP、LDH、KL-6
抗核抗体、リウマチ因子、抗CCP抗体、抗ARS抗体、抗Jo-1抗体、抗Scl-70抗体、セントロメア抗体(抗核抗体で代用しても良い)、抗SSーA抗体、など
経過が急速で呼吸不全があるなら、抗MDA-5抗体は確認必須。
CRPが陽性である病態ならMPOーANCA
他病態の鑑別のため、病原体検索に加えてBNP、CEA、CA19-9、ACEなども検査を考慮。
IgG/IgA/IgMも測定しておくと役立つことがある。
経過と治療
経過
ほぼ正常の肺に急速に発症する、緩徐に発症する(繊維化までゆっくり突き進む、増悪寛解を繰り返してゆっくり進む)、もともとある慢性IPが急性に増悪する、といった臨床経過パターンをとることが多い。
急性では急性呼吸不全に、慢性でも構造破壊が著しくなり酸素投与を必要とするような末期慢性肺疾患(±肺高血圧症)になる。
治療に反応しにくい場合は、常に病態鑑別の見直し、病態の重複などを考慮する。
治療
急速増悪し呼吸不全となっているときは、ステロイドパルスがなされることが多いが、脳神経内科病態でやられるような「パルス単独」ではうまくいかない(どころか施行後のリバウンド的増悪がありうる)ことがあり、初期から積極的に免疫抑制薬を併用するのが良い。
かといって免疫抑制薬だけでは戦えないのでステロイドは後療法をすることになる。
感染症(→治療しなければ悪化)、薬剤性(→気づいて注視しなければ改善しない)、悪性腫瘍(→気づかなければ予後や患者説明に関わる)は、治療がうまくいかないときに考慮する。
基本はステロイド・免疫抑制薬だが、抗繊維化薬がすでに登場している。
ピルフェニドン、ニンテダニブが使用できる。
副作用はあるが、とりわけ処方しにくい薬剤ではなく、治療の選択の一つとなって今後の知見拡大が期待される。

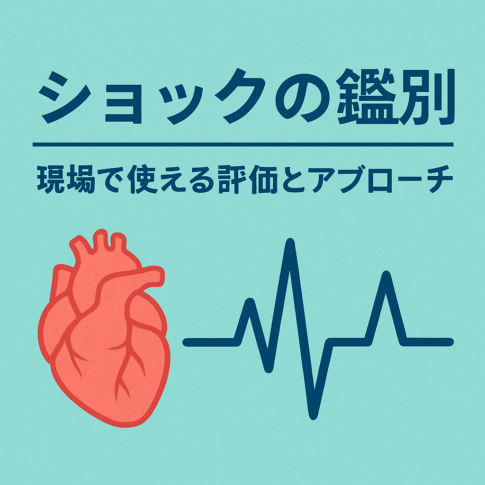
コメントを残す