Contents
🧬 週1回インスリン「アウィクリ注(インスリン イコデク)」
― 高齢者への使用における実践的ポイント ―
2024年4月、日本老年医学会と日本糖尿病学会は共同で「高齢者における週1回持効型溶解インスリン製剤使用についてのRecommendation(推奨)」を公表しました。これは、週1回投与型の基礎インスリン「アウィクリ注(インスリン イコデク)」を高齢者に安全かつ有効に使用するための実践的なガイダンスです。
🧓 高齢者での使用にあたっての「5つの実践ポイント」
- 適切な治療目標の設定
- 高齢者は低血糖症状に気づきにくく、重症化しやすいため、**日本老年医学会の「高齢者糖尿病の血糖コントロール目標」**に基づいた、やや緩やかなHbA1c目標が推奨されます。
- 脳血管疾患歴や認知機能、ADL(日常生活動作)の低下を加味し、個別に目標設定する必要があります。
- 適切なタイミングでの血糖モニタリング
- 特に投与後2〜4日目に低血糖リスクが高まるため、モニタリングはこの期間に重点を置く。
- SMBG(自己血糖測定)や、可能であれば持続血糖モニタリング(CGM)の活用も考慮。
- 訪問看護・介護環境での使用
- 週1回の投与は、訪問看護や介護サービスと非常に相性が良い。
- 看護師が訪問時に投与すれば、自己注射が困難な患者にも対応可能。
- 誤投与(例:毎日投与してしまう等)を避けるために、スケジュール管理の徹底が必須です。
- 感染症や術前の血糖管理
- 長期間作用する薬剤のため、急性疾患(発熱、脱水など)や手術前には血糖コントロールが難しくなる可能性がある。
- 必要に応じて一時的な中止や、他のインスリン製剤への切り替えを考慮。
- 低血糖の予防と対応
- 高齢者は自覚症状に乏しいため、本人・家族・介護者への事前教育と対応マニュアルの共有が重要。
- 低血糖症状が出にくいことを前提とし、疑われる場合には積極的な補食などで対応。
💉 使用時の補足ポイント
- 切り替え時の用量について
- 既存の持効型インスリン(例:トレシーバ等)から切り替える場合、通常は1.5倍に増量が推奨されています。
- ただし、高齢者ではこの増量が低血糖リスクを高める可能性があるため、必ずしも増量せずに同量スタートすることも選択肢とされています。
- 10単位刻みでの調整
- 細かい単位調整ができないため、インスリン感受性が高い方や体重が軽い方には慎重な適応判断が必要です。
✅ 高齢者医療における利点
- 注射回数が減り、治療継続のハードルが下がる
- 訪問診療や訪問看護とスケジュールが合わせやすい
- 認知機能低下がある場合も、支援体制があれば導入しやすい
⚠️ 導入に際しての注意点
- 投与曜日の管理、確認は厳密に行い、誤投与防止の体制を整えることが必要
- 医師・訪問看護師・介護スタッフ・家族間での情報共有と連携が成功の鍵
- 適応となる患者像は限定的で、導入の判断は慎重に行うべきです
📝 まとめ
アウィクリ注は、高齢者の糖尿病治療において、新しい選択肢を提供する可能性のある製剤です。しかし、高齢者は低血糖のリスクや急性増悪時の対応が難しくなるため、使用には十分な注意が必要です。
日本老年医学会・糖尿病学会が提示した5つのポイントを踏まえ、**「安全・簡便・連携」**をキーワードに、慎重かつ柔軟に導入を検討することが重要です。
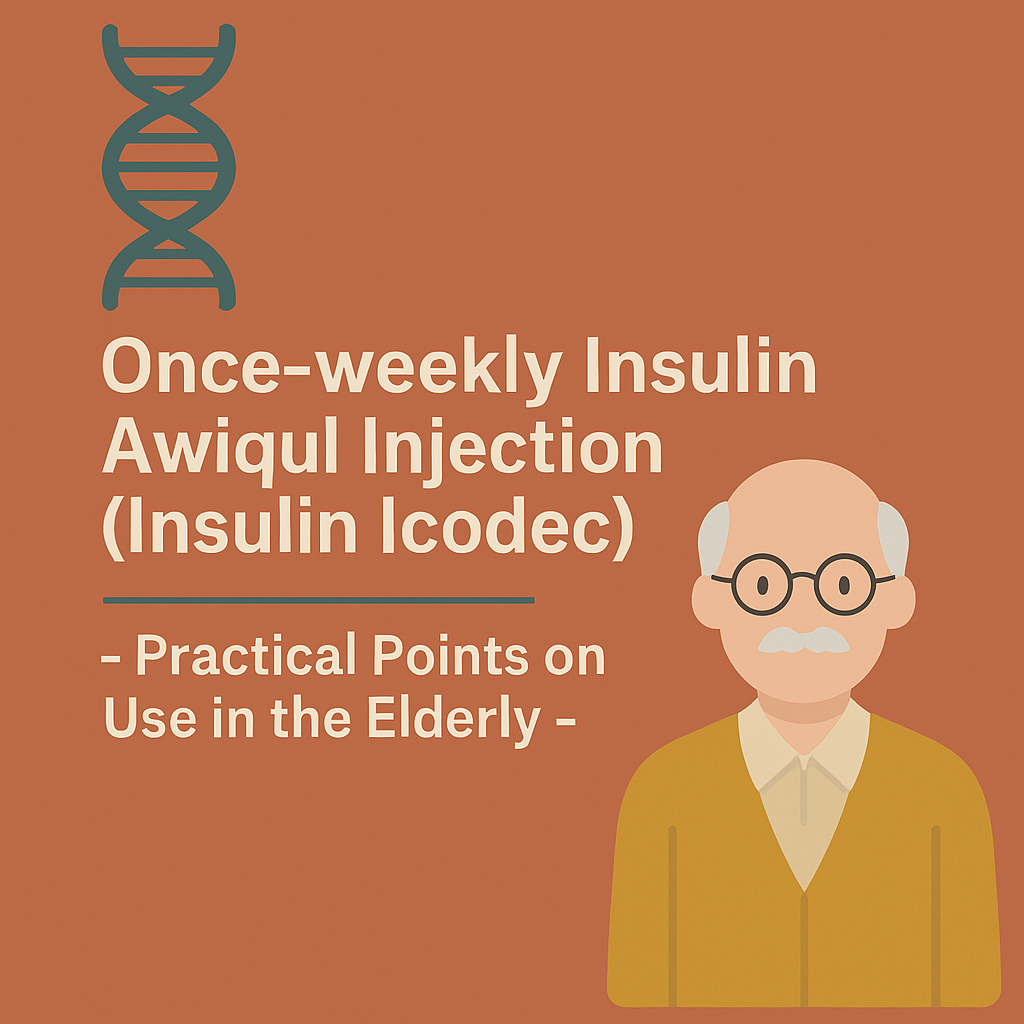

コメントを残す