失神(syncope)は突然の意識消失で始まる緊急性の高い主訴の一つです。一見良性に見えることもありますが、命に関わる重大な疾患の初発症状である場合も。今回は、失神のアプローチを、現場で迷わないための実践的フローとしてまとめました。
🩺 参考リンク:
Contents
第1章:失神とは
■ 定義
失神は、「大脳半球の一過性の低灌流により生じる意識消失」であり、短時間で完全に回復することを特徴とします。
- 突然発症
- 意識消失の持続時間は短く(多くは数秒〜数分)
- 自然に完全回復
- 発作中の記憶がない(健忘あり)
- 運動制御・姿勢保持も障害される(転倒しやすい)
これに対し、けいれんや代謝性の意識障害(例:低血糖)などは、失神とは区別されます。
第2章:失神か、それ以外か? – TLOC(transient loss of consciousness)の鑑別
まずは、「一過性意識消失(TLOC)」全体を鑑別する必要があります。
■ 分類
- 失神(syncope)
→ 大脳の低灌流による一過性意識消失。
分類:
1. 神経調節性(迷走神経反射、排尿・排便後など状況失神)
2. 起立性低血圧(薬剤性、出血、自律神経障害・糖尿病・高齢者・神経変性疾患など)
3. 心原性(不整脈・構造的心疾患など) - 非失神性TLOC
→ 失神とは異なる病態。
例:
・てんかん
・心因性(精神疾患・パニックなど)
・代謝性(低血糖など)
第3章:初期対応の流れ – 「失神のアプローチ」
- 病歴よりTLOCを疑う
- 失神 vs 非失神性TLOC の鑑別
- 初期評価(病歴・身体診察・心電図・血圧)
- 高リスク所見の有無を判断 → リスク層別化
高リスク患者
・新規発症の胸部不快感、呼吸困難感、腹痛、頭痛
・労作時や仰臥位での失神
・突然発症の動悸直後の失神
・前駆症状がなく、回避行動がない
・若年の心臓突然死の家族歴
・座位での失神
- 必要に応じて精査・入院・治療を行う
第4章:失神の病歴聴取 – 超重要ポイント
■ 特に重要な病歴要素:
- 前兆:ふらつき、悪心、嘔気、発汗、視野狭窄など(神経調節性を示唆)
- 発作時の状況:立位・排尿後・痛み・咳嗽など(迷走神経反射)
- 既往歴:心疾患、不整脈、失神の家族歴(Brugada症候群など)
- 目撃情報:痙攣・チアノーゼ・持続時間(非失神性を示唆)
第5章:リスク層別化の方法
■ San Francisco Syncope Rule(CHESS)
以下のうち1つでも当てはまれば、7日以内の重篤イベントリスクが高く、入院が推奨される:
| 項目 | 略語 |
|---|---|
| 心不全の既往 | C: Congestive heart failure |
| Ht <30% | H: Hematocrit |
| 心電図異常 | E: ECG |
| 呼吸困難 | S: Shortness of breath |
| 収縮期血圧 <90 mmHg | S: Systolic BP |
感度96%、特異度61%
第6章:高リスク所見と危険な失神の見極め
■ 病歴・身体所見で危険を示唆する所見
- 胸痛、動悸、呼吸困難
- 労作時の失神、心疾患の既往
- 頻脈・徐脈・収縮期血圧 <90 mmHg
- 持続する意識障害(けいれんや頭部外傷を伴う場合も)
■ 心電図での高リスク所見
- 徐脈(<40bpm)、房室ブロック(Mobitz II型、第3度)
- Brugada型波形、QT延長、デルタ波
- 心筋梗塞の痕跡、ICD・ペースメーカ装着者
第7章:精査の選択
■ 超音波検査(心エコー)
- 弁膜症、左室機能低下、心筋症、心タンポナーデ、肥大型心筋症、肺高血圧などを評価
■ 起立試験(orthostatic BP)
- 起立後3分以内に収縮期血圧が20mmHg以上低下、または90mmHg未満 → 起立性低血圧と診断
■ ループレコーダー(ILR)
- 原因不明の反復性失神、または高リスク所見がある場合に考慮
第8章:治療とフォローアップ
■ 治療の原則:
| 原因 | 治療 |
|---|---|
| 神経調節性失神 | 教育・脱水回避・ミドドリン(4–8mg分2) |
| 起立性低血圧 | 塩分・水分摂取、弾性ストッキング、内服(ミドドリンなど) |
| 徐脈性不整脈 | ペースメーカー |
| 頻脈性不整脈 | 抗不整脈薬・アブレーション・ICD |
| 虚血性心疾患 | PCI、CABGなど |
| HOCM、Brugadaなど | カテーテル治療、ICD |
第9章:退院前アクションプラン
- 原因不明のまま退院する場合もあるが、致死性疾患の否定が前提
- 総合内科・循環器・神経内科との連携を
おわりに
失神は「ただの立ちくらみ」と見過ごされがちですが、心電図異常や心疾患の存在があれば予後に大きく影響します。San Francisco Syncope Ruleを使ったリスク層別、初期評価の徹底、そして必要な精査・治療の選択が重要です。
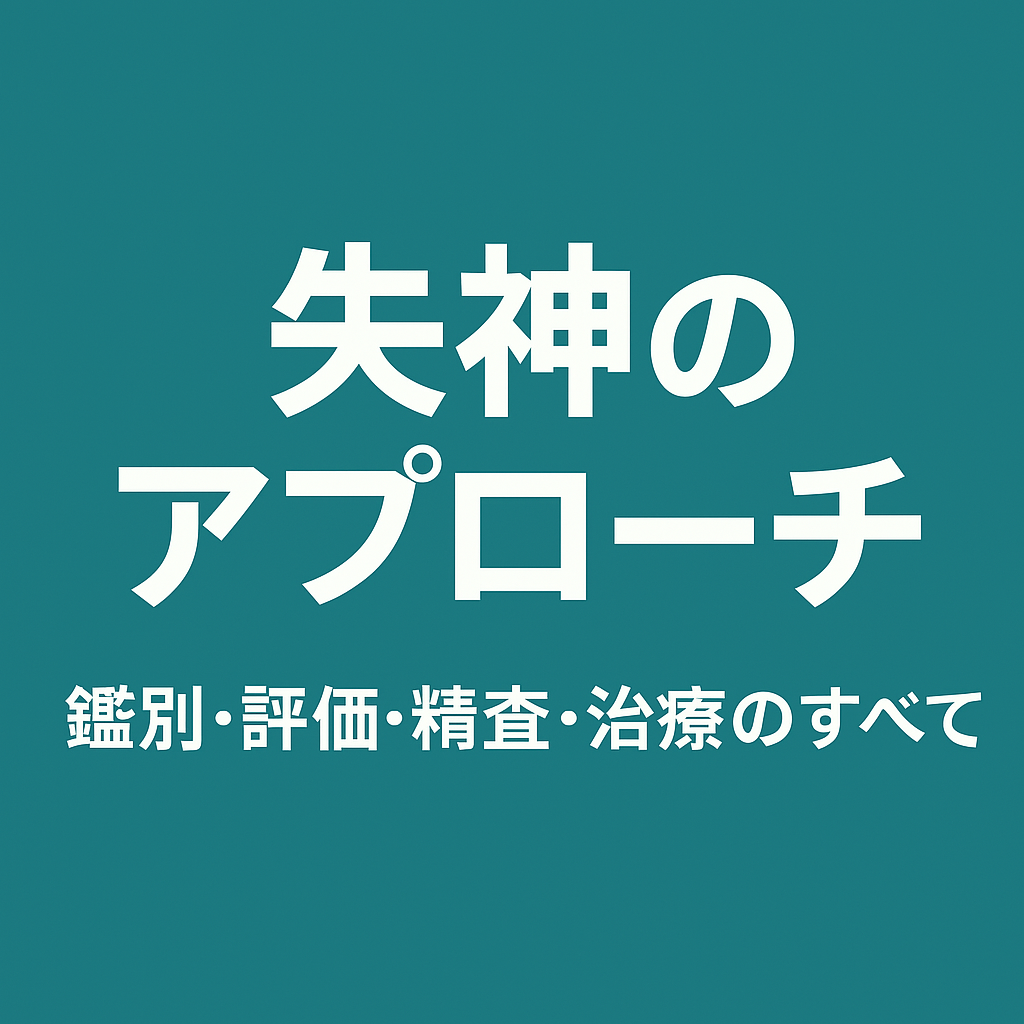


コメントを残す