Contents
胃瘻による栄養補給の医療的効果
栄養状態の改善と全身状態への影響
経皮的内視鏡下胃瘻造設術(PEG)による経管栄養は、食事摂取が困難になった認知症患者に対し、栄養と水分を直接胃に補給する方法です。理論上、PEG栄養により栄養状態を維持・改善できれば、体重減少の抑制や脱水予防につながり、全身状態の安定化が期待されます。また十分な栄養は免疫力の維持や褥瘡の治癒促進にも寄与し得ます。しかし、進行した認知症の患者においては、経管栄養によるこれらの効果は必ずしも明確ではありません。近年の系統的レビューでは、重度認知症患者においてPEG栄養が栄養指標の改善につながる確かなエビデンスは乏しいとされていますcochrane.org。実際、2021年のCochraneレビューでは「経管栄養が患者の栄養状態を改善するという証拠は認められなかった」と結論付けられていますcochrane.org。一方で、認知症患者にPEGを施行した日本の大規模調査では、栄養補給により状態が改善し経口摂取機能が18.4%の患者で改善したとの報告もあります(早期の認知症段階でPEGを行った群ほど改善率が高い)peg.or.jp。このことから、認知症の中等度の段階で一時的にPEGによる栄養サポートを行い全身状態の立て直しを図ることは一定の意義があるものの、重度段階では栄養状態の劇的改善は得られにくいと考えられますpeg.or.jppeg.or.jp。
褥瘡(床ずれ)への影響
PEG栄養により低栄養が是正されれば、褥瘡の予防や治癒促進に寄与すると期待されます。しかし、重度認知症患者を対象とした検討では、PEG栄養を行った群で新たな褥瘡の発生リスクがむしろ増加したとの報告もありますcochrane.org。2021年のCochraneレビューによれば、PEG造設によって褥瘡発生率がわずかに増加する可能性が示されており、この点について中等度の確信度のエビデンスがあるとされていますcochrane.orgcochrane.org。この原因として、経管栄養を行う患者はベッド上で過ごす時間が長くなることや、拘束の使用による活動低下などが考えられます。したがって、PEGによる栄養補給だけで褥瘡リスクを十分に低減できるわけではなく、体位変換や皮膚ケアなど包括的な褥瘡対策が不可欠です。
誤嚥性肺炎の予防効果
嚥下障害のある認知症患者では経口摂取を続けると誤嚥性肺炎のリスクが高まるため、PEGによる経管栄養は誤嚥性肺炎の予防策になると考えられてきました。経口摂取を中止し胃瘻からの栄養に切り替えることで、食物の気道誤嚥を避けられるという理屈です。しかし実際には、胃瘻を造設しても誤嚥性肺炎の発生を完全には防げません。唾液や胃内容物の逆流による誤嚥は引き続き起こり得るためです。複数の研究を総合すると、経口摂取を介助しつつ継続した場合とPEG造設を行った場合で、死亡率や誤嚥性肺炎の発症率に有意差がなかったことが報告されていますnote.com。米国の老年医学会の見解でも、胃瘻が誤嚥性肺炎の予防に寄与しないことが指摘されていますpeg.or.jpigaku-shoin.co.jp。一方、日本の研究からは経管栄養開始後に肺炎エピソードや抗生剤使用が減少したとの報告もありますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。例えば2017年のTakenoshitaらの研究では、重度認知症患者にPEG等の経管栄養を導入した後、誤嚥性肺炎の発生頻度が有意に減少したとされていますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。しかし著者らも「だからといって直ちに全例に経管栄養を導入すべきという意味ではなく、導入の際には患者のQOLを慎重に考慮すべきだ」と述べておりpubmed.ncbi.nlm.nih.gov、誤嚥性肺炎予防だけを目的に機械的にPEG造設を行うことには慎重な姿勢が示されています。
その他の利点と影響(安寧・機能面)
PEGによる人工栄養が患者の安寧(快適さ)や機能面に与える影響についても検討されています。理論上、十分な栄養が供給されれば力が出てADL(日常生活動作)が向上したり、意識レベルが改善したりする可能性があります。国内の前述の調査(PDNの2010年調査)では、PEG造設後に生活自立度が改善した患者が8.5%存在し、認知症の比較的早期にPEGを行った場合ほど自立度の改善が期待できると報告されていますpeg.or.jp。また経口摂取能力についても約18%の患者で改善がみられ、こちらも早期施行群で改善例が多かったとされていますpeg.or.jp。このように、一部の患者では経管栄養導入により状態が安定し、口から食べる機能や日常動作がわずかながら向上する場合もあります。ただしこれらは軽度~中等度の認知症で一時的な体力回復が見込めるケースに限られると考えられますpeg.or.jp。重度のアルツハイマー型認知症患者では、PEG栄養によって認知機能やADLが改善するエビデンスはなくcochrane.org、むしろ患者本人の快適さや尊厳を損なうリスクが指摘されていますigaku-shoin.co.jp。2010年の米国ASPENの声明でも、重度認知症患者において人工的栄養補給を行っても褥瘡の改善、誤嚥性肺炎リスク軽減、患者の安寧や機能改善、生存期間延長のいずれのメリットも証明されていないとされていますpeg.or.jp。したがって、特に進行した認知症の段階では、PEG造設による医療的メリット(栄養・合併症予防・機能維持)は限定的であると認識する必要があります。
胃瘻造設に伴う主な合併症とリスク
PEG造設および胃瘻からの経管栄養には、以下のような合併症やリスクも伴います。
- 感染症・瘻孔部のトラブル:造設部位の皮膚発赤や感染、肉芽増生などの瘻孔部合併症は頻度の高い問題です【33†】。胃瘻周囲の皮膚炎や感染が起こると処置や抗生物質の投与が必要になる場合があります。重症例では腹膜炎に至るリスクもあり、日々の清潔管理が重要です。
- チューブの閉塞・逸脱:経管栄養チューブが詰まったり抜けたりするトラブルも少なくありません。チューブ閉塞時は交換が必要となり、抜去・逸脱した場合は再挿入や場合によっては再造設のための入院処置が必要です。認知症患者では本人がチューブを自己抜去してしまうケースもありigaku-shoin.co.jp、その防止のため身体的拘束や鎮静剤の使用に頼らざるを得ない状況も生じます。このような拘束は患者の尊厳を損ないQOLを低下させるだけでなく、活動性の低下による二次的な廃用症候群や新たな褥瘡発生につながるリスクがありますigaku-shoin.co.jp。
- 消化管・呼吸器系への影響:経管栄養の速度や内容によっては嘔吐や下痢など消化器症状を引き起こすことがあります。また胃内容の逆流により誤嚥が生じれば誤嚥性肺炎の原因となります(前述のとおり、PEG造設後も誤嚥リスクは依然残存します)。長期の経管栄養では胃酸分泌過多による胃潰瘍や、腸管の蠕動低下による便秘も問題となりえます。
以上のように、PEGによる栄養補給には一定の医療上のメリットが期待できるものの、同時に各種合併症リスクや管理上の負担を伴います。特にアルツハイマー型認知症の終末期患者では、得られる利点よりも合併症や苦痛の増大が勝る可能性があるため、慎重な適応判断が求められますjstage.jst.go.jp。
胃瘻増設が生命予後に与える影響
胃瘻造設の延命効果と臨床研究の結果
PEG造設がアルツハイマー型認知症患者の生命予後(生存期間)に与える影響については、国内外で意見が分かれています。栄養・水分補給が維持されれば生命を一定期間延長できることは直感的に理解できますが、その延長効果の大きさや有意義さが問題となります。
海外の研究では、重度認知症患者においてPEGなどの経管栄養を行っても生存期間の有意な延長効果は認められないとの報告が多くありますpeg.or.jpcochrane.org。たとえば2014年のレビューでは「進行した認知症患者へのPEGは予後を改善しない」とされ、2019年のイタリアからの報告でも「経管栄養を行った群の方が経口のみの群より生存率が低く、経管栄養実施自体が死亡の独立したリスク因子であった」と報告されていますpeg.or.jp。また前述のCochraneレビュー(2021年)は、観察研究のデータから**「PEG造設により寿命が延びるという明確な証拠は無い」と結論付けていますcochrane.org。このレビューでは、PEG実施群と非実施群で生存期間に差が見られなかった研究が多く、むしろPEG実施群で褥瘡が増える傾向が確認されていますcochrane.orgcochrane.org。さらに米国老年医学会など複数の専門学会は、進行した認知症患者への経管栄養を「延命効果が乏しく有害になり得る低価値医療」と位置付け、原則行うべきでない**との立場を表明していますigaku-shoin.co.jpnote.com。実際、“Choosing Wisely”キャンペーンにおいても「高度認知症に胃瘻は推奨されず、代わりに慎重な手送りによる経口栄養を続けるべき」と勧告されていますigaku-shoin.co.jp。
一方、日本国内の研究ではPEGの生命予後に対する一定の効果を示唆するデータも報告されています。日本のNPO法人PDNが2010年に行った1,000例超の調査では、PEG造設後の50%生存期間が約847日(2年4か月)と算出され、これは海外報告と比較して著しく長い生存期間であったと報告されていますpeg.or.jp。同調査では「PEGは認知症の早期・晩期を問わず生命予後の改善に寄与する」と結論づけられており、日本人高齢者ではPEGにより延命傾向が顕著であるとされていますpeg.or.jp。さらに岡山県の9病院からの報告(Takayamaら, 2017年)では、経管栄養(PEGまたは経鼻)を行った認知症・精神疾患患者185例の中央値生存期間が711日だったのに対し、経管栄養を行わなかった群では中央値61日と極めて短く、大きな予後差が確認されましたpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。特にPEGを造設したサブグループでは中央値で1,000日以上生存しており、経鼻経管栄養よりPEGの方が安全で予後が良好であったと報告していますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。また同年の別の研究(Takenoshitaら, 2017年)でも、重度認知症患者58例の検討で経管栄養実施群の生存期間中央値が23か月だったのに対し、非実施群は中央値2か月と報告されており、経管栄養開始が明らかな延命につながったと述べていますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。これら国内の結果は、極端に言えば「PEGをするか否かが**“延命するか否か(生きるか死ぬか)”に直結する」ことを示唆していますpeg.or.jp。実臨床でも、嚥下障害が進行して経口摂取不能となった認知症患者では、PEG等で人工的に栄養補給を続ければしばしば数ヶ月~数年の生命維持が可能になる一方、栄養補給しなければ比較的短期間で看取りとなるケースが多いのが現状です。
以上を総合すると、生命予後に関するPEGの効果は見る視点によって異なります。栄養を補給しなければ数週間~数ヶ月で死亡する可能性が高い終末期患者に対しては、PEGは確実に生命を“延長”させる手段と言えます。一方で、延長された寿命の質やそれが患者本人の望むところかという観点では、単純に「延命=利益」とは限りません。海外の文献が示すように、PEGによって統計的な長期生存率の有意な改善が得られない背景には、PEGで延命したとしても基礎疾患の進行に伴う全身状態悪化を避けられず、結果的な最終予後は大きく変わらないことが関与している可能性があります。またPEG造設群と非造設群の比較はランダム化が困難なため、患者背景の違い(例えば非造設群はより重篤であった等)が結果に影響している可能性も指摘されていますcochrane.org。現在得られているエビデンスからは、「PEG造設で長期予後が必ずしも改善しない」こと、そして「延命できてもその間のQOLに課題がある」ことが示唆されており、延命治療としてのPEGの効果には明確な限界があるといえますcochrane.orgigaku-shoin.co.jp。
認知症進行度(中等度 vs 重度)による効果の差
アルツハイマー型認知症患者へのPEGの効果は、その時点の認知症の進行度によって大きく異なる可能性があります。中等度(比較的初期~中期)の認知症であれば、例えば他の合併症や一過性の摂食嚥下障害によって一時的に食べられなくなった際にPEGで栄養補給を行い、体力や嚥下機能が回復した段階で経口摂取に戻すというシナリオも考えられますpeg.or.jp。ESPEN(欧州静脈経腸栄養学会)のガイドライン(2015)でも、軽度~中等度の認知症で栄養改善により全身状態の回復が見込める場合には、期間限定で人工的水分・栄養補給(AHN)を行うことが容認されるとしていますpeg.or.jp。実際、日本の調査でも認知症の比較的早期にPEG造設を行った群でADLや経口摂取の改善が多くみられたことから、病状が進み過ぎる前の段階で適切に経管栄養を導入すれば一定のリハビリ効果や在宅復帰の可能性も期待できますpeg.or.jp。
これに対し、重度(終末期)の認知症では状況が異なります。嚥下機能の不可逆的な低下や、多臓器の衰弱が進行している終末期では、PEGによる栄養投与は延命措置としての色合いが強くなり、患者本人の意識レベルや活動性が改善する見込みはほとんどありませんcochrane.org。ESPENガイドラインでも重度認知症患者に対しては「経管栄養をすべきではない」との強い推奨がなされており、そのエビデンスレベルは高いとされていますpeg.or.jp。米国老年医学会も同様に、進行期の認知症での胃瘻は推奨されないとのコンセンサスを示していますigaku-shoin.co.jp。重度認知症患者では、経管栄養を導入してもQOLの向上や合併症予防につながらず、かえって前述したような拘束の増加や合併症リスクにより苦痛を長引かせる可能性がありますigaku-shoin.co.jpnote.com。日本老年医学会が2012年に公表した高齢者ケアのガイドラインでも、終末期においてPEGを含む医療行為が患者の尊厳を損なう恐れがある場合には、その治療を差し控える(開始しない)ことや中止することも選択肢として明記されていますjstage.jst.go.jp。実際、日本国内のアンケート調査でも、多くの高齢者や医療者が「認知症が進行した場合、中心静脈栄養や胃瘻による延命は望まない」と回答しておりnote.com、重度認知症では患者本人の意思に沿って経管栄養を行わず自然な経過を看取ることが尊重されつつあります。
臨床ガイドラインの記載内容
以上を踏まえ、国内外の臨床ガイドラインでもアルツハイマー型認知症患者へのPEG増設について慎重な姿勢が示されています。日本老年医学会の**「高齢者ケアに関する意思決定プロセスのガイドライン」(2012年)では、重度認知症など人生の最終段階にある高齢者について、人工的水分・栄養補給の導入の是非は本人の意思や利益を最優先に考慮し、PEGを含む経管栄養が患者の尊厳を損なう場合には実施しない選択**を含めて検討すべきとされていますjstage.jst.go.jp。また栄養管理に関する多職種ガイドライン(日本老年歯科医学会など)でも、認知症末期の経管栄養はQOLや予後を改善しないことから無理に行わない旨が記載されています。厚生労働省の資料でも、認知症が進んだ場合に多くの人が経管栄養を希望しない実態が示されておりnote.com、医療現場でも本人・家族と事前に十分話し合い(アドバンス・ケア・プランニング)を行って方針を決定することが推奨されています。
一方、海外のガイドラインではさらに明確に、進行した認知症への経管栄養を否定する記載が見られます。前述の**ASPEN倫理声明(2010年)や米国老年医学会(AGS)**の声明では「重度認知症では経管栄養の適応なし」と断言されておりpeg.or.jpigaku-shoin.co.jp、ESPENガイドライン(2015年)でも「重度認知症患者に経腸栄養を行うべきではない」と強く推奨していますpeg.or.jp。AGSの2014年の声明では「進行した認知症患者に経腸栄養(PEG)は推奨されず、慎重な手による食事介助を続けるべき」と明記され、これはChoosing Wiselyキャンペーンの5項目にも採択されていますigaku-shoin.co.jp。これら国際的なガイドラインは、PEGによる延命よりも自然な経口摂取とケアによる緩和的なアプローチを重視する流れを反映しています。
総じて、アルツハイマー型認知症患者に対する胃瘻造設はケースバイケースで慎重に判断すべき医療行為です。中等度までの段階で一時的に栄養補給し患者の状態改善を図る目的では一定の効果が期待できますが、重度・終末期では延命効果に限界があり、患者のQOLや尊厳への影響が大きいことからガイドライン上も推奨されていませんigaku-shoin.co.jpjstage.jst.go.jp。最新のエビデンスとガイドラインを踏まえ、患者本人と家族の意思を尊重したうえで、PEG造設の適否を多職種で検討することが重要です。
参考文献: 胃瘻造設に関する国内外の研究論文および厚生労働省・専門学会のガイドライン等
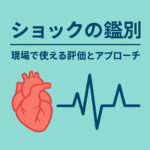

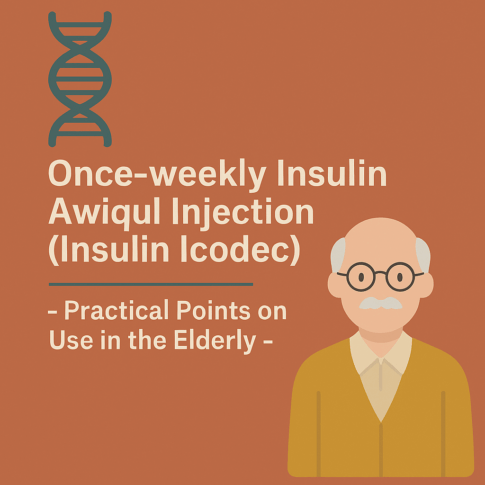
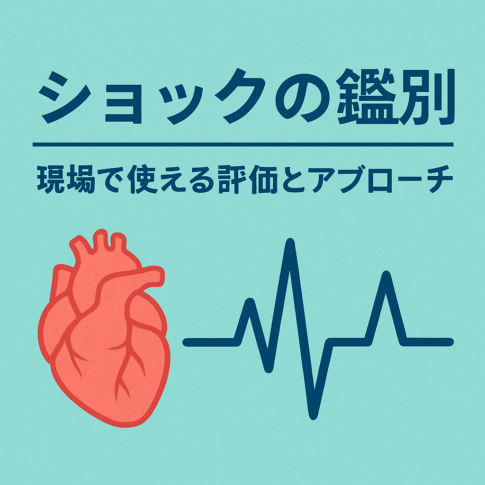
コメントを残す