概要
血中の好酸球増加を伴って、さらに好酸球が肺実質や間質にまで浸潤する疾患である。
原疾患があるものと、ないもの(特発性)がある。
原因・原疾患があるものは、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、薬剤性、寄生虫関連、アレルギー性気管支肺アスペルギルス症などがある。好酸球性増多症候群による好酸球性肺炎も、原因ありの方に含める。
特発性には、急性と慢性があり、それぞれに臨床的な特徴や傾向がある。
好酸球性肺炎は20歳前後の若い男性に多く、典型的には初めての喫煙習慣から数日経過で発症するもので、咳、発熱、呼吸困難、胸膜痛などを生じる。
血中好酸球が高いことは必ずしも前提とはならず、臨床では、血液検査よりも肺画像が印象的となる(こちらが好酸球性肺炎の前提的特徴でもある)
喫煙だけでなく、何らかの吸入歴(粉塵吸入など)と関係しているとされ、気管支喘息などのアレルギー疾患の既往・合併などとは関係がないとされる。
慢性好酸球性肺炎肺炎は30~40歳台の女性に多く、症状は急性同様肺炎様である。
急性好酸球性肺炎と違い、末梢好酸球増多が見られやすい。
気管支喘息やアレルギー性鼻炎などのアレルギー疾患を随伴あるいは先行していることが多い。
じとっと弱い症候を長く引きずるというより、発作の様なエピソードを細かく反復する(再発を繰り返す)ことを持って「慢性」であると称しているものと思われる。
不明熱っぽく捉えられることもある。
好酸球性肺炎は、本書でいうところの「症候的疾患」に近い。
特発性に限って、つまり疾患単位で考えた場合には、そこまでコモンな疾患ではなく比較的稀な疾患である。
疑い方
咳・発熱・呼吸困難を呈し、(正気の)診療をしていればほぼ必ず肺画像検査に至るような症状で受診する。
急性では普通、受診閾値は容易に超える。
本病態であれば、肺浸潤影が目立って認められるので、臨床医はほぼ肺に関心が向く。ここを見逃すことは考えられない。
すなわち、初期は感染症性肺炎の様相で始まり、治療に不応であるため肺画像の原因鑑別作業をし直す、という臨床的雲行きになることが多い。
末梢血好酸球増多があれば診断を勧めやすいが、大概はわりと早い段階で胸部異常影に気づかれて呼吸器内科マターとなるため、実地医家が取り扱うことの少ない疾患である。
診断は、画像(特にCT)パターンで推定、気管支肺胞洗浄(BAL)や経気管支肺生検(TBLB)、除外診断を持って行われる。BALは好酸球分画の増加、TBLBは好酸球浸潤を確かめる。
経過と治療
急性型では著しい低酸素血症となることがある。
人工呼吸器を要するレベルの場合は、通常はステロイドパルス療法や高容量ステロイドで急場を凌ぐことが多い。
ただし、あまりに(血中あるいは組織中に)好酸球増多が強く見られると思われる場合は、パルスはその後の反動(リバウンド的なもの)も怖い。
生命の危機に瀕している場合以外は、内服プレドニゾロンで良いと思われ、血中好酸球が消失〜少なく抑えられているのに肺浸潤の治りが悪いような時には、パルスではなく(難治喘息とみなして)ベンラリズマブの導入を考慮する。
慢性好酸球性肺炎では、一気に予後不良ん異なることは少ないが、増悪・寛解を繰り返して間質性肺炎を見ているような経過になることがある。その場合は、ステロイドの積算的な副作用は無視できない。
増悪時にはやはりプレドニゾロンを用い、またそれに反応はしやすい。よって少なくともステロイドパルスは大袈裟である。
末梢血好酸球増多が制御しにくい時に考えるのは、1:起点から診断を見直す、2:侵襲的な検査をしていない場合にはそれらを行う、3:メポリズマブの導入を検討する、である。
例えば、呼吸不全の原因が肺ではなく実は心臓(好酸球性心筋炎)だったなど、病態の本質を見誤っていることがある。
急性好酸球性肺炎は「トリガー+反応性病態」が本態と思われるため、経過が良ければステロイド治療期間は2〜3週で漸減・中止させる(これで経過が悪ければ診断を見直す)
慢性は、慣習的には中等量を6〜12ヶ月かけて漸減中止することが行われている様だが、それが正しいかどうかはわからない。
慢性好酸球性肺炎は、治療・マネジメントについてはまだ課題の多い疾患である。

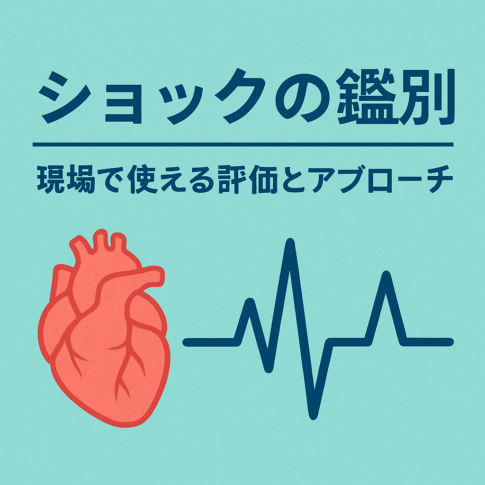
コメントを残す