Contents
はじめに
高カリウム血症は、救急外来や病棟で頻繁に遭遇する病態である。特に心電図変化を伴う場合は、迅速な対応が求められる。本記事では、総合診療医の視点から高Kの診断と治療の流れを解説し、実践的なマネジメントのポイントを示す。
なお当ブログの内容は、一般的な医療情報の提供を目的としており、個別の診断・治療を目的としたものではありません。症状や治療についての最終的な判断は、必ず専門の医師とご相談ください。
この記事を書いている人↓
またこの記事は高カリウム血症に関して解説している。過去に低カリウム血症についても解説しているので興味があれば、下記記事を参照いただきたい。↓↓↓
症例:慢性腎臓病患者の高カリウム血症
75歳男性。高血圧と慢性腎臓病(CKDステージ4)の既往がある。朝食後にふらつきと倦怠感を自覚し、救急外来を受診した。
診察時の血圧は98/60 mmHg、脈拍は52 bpmと徐脈を呈している。心電図ではテント状T波とPQ間隔延長がみられた。血液検査でK⁺6.8 mEq/Lと判明し、高カリウム血症の診断となった。
高カリウム血症の治療戦略
高K(高カリウム血症)は、迅速な対応が求められる病態であり、特に心電図変化を伴う場合には緊急介入が必要である。今回の症例では、以下の流れで治療を進めた。
① 不整脈予防:カルシウム投与
K⁺が6.5 mEq/Lを超え、心電図異常も認められたため、まずはグルコン酸カルシウム(10% 10 mL)を3分かけて静注した。これは、カリウムによる心筋興奮性亢進を抑え、不整脈のリスクを軽減するためである。
② カリウムの細胞内移動促進
高Kを是正するためには、カリウムを細胞内へ移動させるアプローチが有効である。そこで、
- 速効性インスリン5単位 + 50%ブドウ糖液40 mL静注
- β2刺激薬(サルブタモール10 mgネブライザー)
を併用した。特にインスリンとブドウ糖は速効性があり、救急外来で即座に使用できるため有用である。
実際にはβ2刺激薬の吸入は添付文書上での使用方法ではないため、また投与量としても添付文書に記載されている気管支喘息に対する使用を逸脱した量となるため、自分自身使った経験はない。
またGI療法に関しては教科書的にはインスリン投与量はかなり幅がある。インスリン量はブドウ糖5gにつき1単位ぐらいが妥当と考えている。高K旧正規治療中に治療による低血糖の合併症を起こすことはできる限り避けたい。そのため上記療法を繰り返し行うか、持続点滴として1号液を使用するなどしている。
③ カリウムの排泄促進
腎機能低下に伴いカリウム排泄能が低下しているため、ループ利尿薬とカリウム吸着薬(ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム10 g内服)を投与した。
④ 原因検索と再発予防
高Kの背景因子を探るため、薬剤歴を確認するとARB(ロサルタン)を服用していた。高Kを助長する可能性があるため、減量または変更を検討した。また、高カリウム食(バナナ・トマト・じゃがいも)の制限についても指導を行った。
初期マネジメント
病歴のチェックはもちろん大事だが、初期治療を迅速に行う必要があるだろう。
高カリウム血症では、食べ物からの摂取量・薬剤歴、腎不全の増悪等の要因をチェックしておく。また食事内容のほか、入院中の患者となれば輸血歴、点滴内容、また溶血の有無はチェックが必要だろう。
評価と初期対応
高カリウム血症の診断においては、病歴の確認が重要であるが、初期治療を迅速に行う必要がある。特に以下の要因を確認する。
- 食事内容:カリウム含有食品の摂取状況
- 薬剤歴:カリウム上昇のリスクとなる薬剤(ACE阻害薬、ARB、ARNI、スピロノラクトンなど)
- 腎機能:腎不全の進行や急性腎障害の有無
- 入院中の患者:輸血歴、点滴内容、溶血の有無
高カリウム血症の補正
- リスクとなる薬剤の中止
- 原疾患の治療(例:腎不全の管理)
- カリウム摂取の制限(K含有食品の摂取制限)
- 心不全患者における考慮:薬剤の中止が難しい場合は、カリウム吸着剤を併用しつつ継続を検討
治療指針
K 5〜6 mEq/L
- 原因への対応(高カリウム血症をきたす薬剤の中止)
- カリウム摂取の制限
- フロセミド投与(利尿によるカリウム排泄促進)
- カリウム吸着剤
- 透析の検討(腎機能低下が著しい場合)
K 6 mEq/L以上
- 心電図評価を優先
心電図変化については下記を参照。MSDマニュアル プロフェショナル版より引用
https://www.msdmanuals.com/ja-jp/professional/10-内分泌疾患と代謝性疾患/電解質障害/高カリウム血症#診断_v8375720_ja
- 血行動態が安定している場合
- GI療法(グルコース・インスリン療法)
- フロセミド
- カリウム吸着剤
- K 7 mEq/L以上 または 心電図異常あり
- カルチコール(グルコン酸カルシウム)10 mLを5分で静注
- ※ジギタリス中毒が疑われる場合は禁忌のため、事前に内服歴を確認
- その後にGI療法、フロセミド、カリウム吸着剤を内服
- カルチコール(グルコン酸カルシウム)10 mLを5分で静注
K 7 mEq/L以上の場合の筆者の対応例
- ソルデム1でルート確保
- カルチコール(グルコン酸カルシウム)2A静注
- GI療法
- 50%ブドウ糖液40 mL + ヒューマリン5U(1〜2回投与)
- ※血糖100未満の場合は低血糖リスクがあるため、ブドウ糖液を追加(20 mL)または30分後に血液ガス評価を実施
- ロケルマ10 g内服(カリウム吸着剤)
- フロセミド20 mg静注
- 2〜3時間後に血液検査を再評価
- カリウム低下が認められなければ、透析導入のため腎臓内科にコンサルト、自施設で透析ができない場合は、透析の対応が可能な医療機関へ転院を相談する。
このように、評価と治療を迅速かつ体系的に行うことで、高カリウム血症のリスクを最小限に抑えることができる。

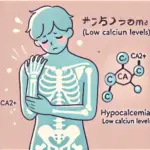



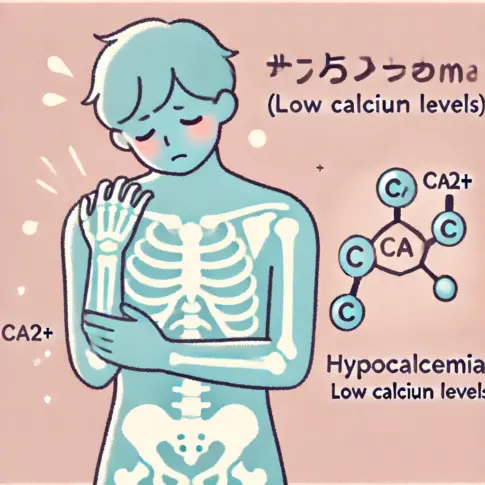
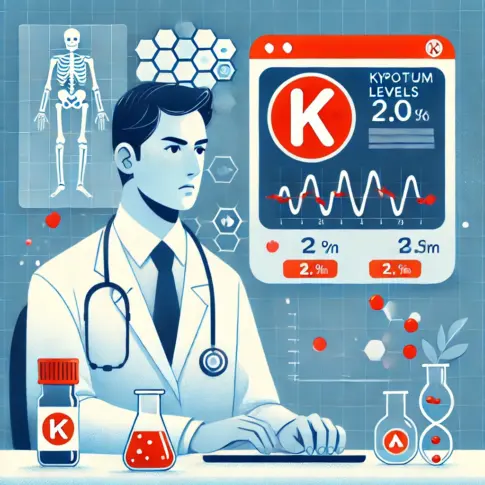

コメントを残す