Contents
はじめに
毎年冬になると猛威を振るうインフルエンザ。多くの患者が発熱や咳などの症状を訴え、医療機関を受診する。特に高齢者や基礎疾患を持つ人にとっては、合併症を引き起こすリスクが高く、適切な治療が求められる。世界では300〜500万件の重症例ち29〜65万人の呼吸器系死亡を引き起こすとされている。
しかし抗ウイルス薬は発症期間の短縮や合併症予防の可能性があるが、最適な薬剤はどれかという結論は出ていない。またWHOの2022年ガイドラインではオセルタミビルが推奨されたが、エビデンスの確実性は低いとされている。
今回、JAMA Internal Medicine に掲載された最新の研究論文 “Antiviral Medications for Treatment of Nonsevere Influenza” をもとに、インフルエンザ治療における抗ウイルス薬の有効性と課題について詳しく解説する。
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2829156
また季節性インフルエンザ自体に抗ウイルス薬が必要か?という命題に対しては今回取り扱っていない。そもそも季節性インフルエンザ自体、他のウイルス感染症と同様に自然軽快する疾患であることが承知の通りだろう。ただ症状消失期間の短縮などのメリットを患者に説明すると、ほとんどの例において処方を希望するのではなかろうか。急性期を過ぎつつあるインフルエンザに対しては、薬の副作用のデメリットを説明して、処方しないケースが多いが、一般的にインフルエンザの急性症状がある場合、筆者自身は抗ウイルス薬を処方することが多く、その中でも何が一番妥当な処方なのかを今回考えたい。
なお当ブログの内容は、一般的な医療情報の提供を目的としており、個別の診断・治療を目的としたものではありません。症状や治療についての最終的な判断は、必ず専門の医師とご相談ください。
インフルエンザ治療の現状と課題
インフルエンザの治療には、主に以下のような抗ウイルス薬が使用される。
- オセルタミビル(タミフル):世界的に広く使用されている内服薬。
- ザナミビル(リレンザ):吸入薬として使用される。
- バロキサビル(ゾフルーザ):単回投与で効果が期待できる新規薬剤。
- ペラミビル(ラピアクタ):点滴で投与される。
- ラニナミビル(イナビル):1日1回の吸入で治療が完結する吸入薬。
- ウミフェノビル:ロシアや中国で使用されている薬剤。
しかし、これらの抗ウイルス薬がどの程度効果があるのか、また副作用や耐性のリスクについては明確な結論が出ていない。そこで、今回の研究では、これらの薬剤の有効性と安全性を比較するため、73のランダム化比較試験(RCT)、計34,332人のデータを網羅したネットワークメタアナリシスが実施された。
Methods
•データソース: MEDLINE, Embase, CENTRAL, CINAHL, Global
Health, Epistemonikos, ClinicalTrials.gov (2023年9月20日まで)
•対象: 抗ウイルス薬 (オセルタミビル、ザナミビル、バロキサビル等)
を標準治療またはプラセボと比較したRCT
•評価項目:
•主要アウトカム: 死亡率、入院率、ICU入室率
•副次アウトカム: 症状軽快までの時間、副作用、耐性出現
•統計解析:Pairwise meta-analysis
エビデンスの確実性
各結果のエビデンスの確実性を評価するために、ネットワークメタ解析のGRADE(Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)アプローチを用いた。バイアス、不正確さ、矛盾、間接性、出版バイアスのリスクを評価し、直接推定値のエビデンスの確実性を高、中、低、または非常に低と評価した。
電子検索により11878件の記録が特定された。 8944件のタイトルと抄録、459件の全文をスクリーニングした結果、73件のRCTを報告した87件の論文が適格であることが証明された。
対象となった試験は、1971年から2023年に発表されたもので、8種類の抗ウイルス薬(バロキサビル、ファビピラビル、ラニナミビル、オセルタミビル、ペラミビル、ウミフェノビル、ザナミビル、アマンタジン)を評価したもの。
研究の特徴
・オセルタミビルと標準治療またはプラセボとの比較が最も多かった。
・65の試験は症状発現から2日以内
・サンプルサイズは14〜3266(合計34332)
・平均年齢の中央値は35.0歳
・男性の割合の中央値は49.8%
・ 転帰の追跡期間は5~29日
研究結果のポイント
1. 抗ウイルス薬は死亡率を改善するか?
本研究によると、いずれの抗ウイルス薬も死亡率にはほぼ影響を与えない ことが明らかになりました。特に、低リスクおよび高リスク患者のいずれにおいても、標準治療やプラセボと比較して統計的に有意な差は見られませんでした。
2. 入院リスクの低減効果
- 低リスク患者:すべての抗ウイルス薬で 入院率の低下は認められず(高確実性)。
- 高リスク患者:
- バロキサビルが入院リスクを 1.6% 減少させる可能性あり(低確実性)
- オセルタミビル、ザナミビルは効果なし(高確実性)
3. 症状軽快までの時間
- バロキサビル:症状軽快までの時間を 1.02日短縮(中等度確実性)。
- ウミフェノビル:1.10日短縮(低確実性)。
- オセルタミビル:0.75日短縮(中等度確実性)。
4. 副作用のリスク
- バロキサビル:副作用なしまたは軽度(高確実性)。
- オセルタミビル:副作用(特に消化器症状)が2.8%増加(中等度確実性)。
5. 耐性の出現
- 1554人の患者が登録された12の試験で、抗ウイルス薬を投与された参加者の耐性出現が報告。
- • バロキサビルは薬剤耐性の出現に重要な影響を与えた可能性がある(割合、9.97%;95%CI、0.02%-31.79%;確信度低)。
- • ザナミビルは薬剤耐性の出現に重要な影響を及ぼさなかった可能性がある(割合、0%;95%CI、0%~11.66%;確信度低)。
- •オセルタミビルとペラミビルが薬剤耐性の出現を増加させたかどうかは不明であった。
臨床的インパクトと今後の展望
今回の研究結果を踏まえると、バロキサビルが高リスク患者において有望な選択肢である ことが示唆される。ただし、耐性ウイルスの出現が懸念されるため、広範な使用には慎重なアプローチが必要だろう。
一方、オセルタミビルは長年使用されている薬剤だが、入院リスクの低下には寄与せず、むしろ副作用が増える可能性があるため、今後の使用ガイドラインに影響を与える可能性があるだろう。
まとめ
- バロキサビルは 高リスク患者の入院率を減少させ(-16/1000)症状軽快時間を短縮する可能性があり、副作用の増加はなさそう。
- ・オセルタミビルは以前から報告されている症状短縮の効果が期待されるが、死亡率や入院率に影響はなく、副作用増加の可能性がある。
- ・バロキサビルは副作用に対して入院率を減少させる可能性があるが、耐性出現リスクをどう判断するか検討が必要。
論文を読んでみて筆者が考える処方
- 入院が必要そう→ラピアクタ(ペラミビル)
理由:ラピアクタは使用例がかなり少なく、エビデンスが乏しいと言わざるを得ない。ただ本論文においてはHigh-risk patientsに対してMortalityは有意差はないものの、減少する傾向にあるように思われる。そのため入院が必要で点滴も選択可能であれば、ラピアクタを選択することが妥当だと考える。
- 入院が不要だがリスクあり→ゾフルーザ(バロキサビル)
理由:ゾフルーザが使用しにくいのはその耐性リスクだろう。だが、抗ウイルス薬の中で唯一副作用を増やさず、入院を減らしている点は評価すべき点である。そのため、外来で治療を行うが、悪化するリスクが大きいと評価する場合は、ゾフルーザを選択することとしている。
- 学童〜若者のリスクなし→イナビル(ラニナミビル)
or リレンザ(ザナミビル)
理由:他の抗インフルエンザ薬についてもそうだが、タミフルは異常行動や幻覚などの副作用が知られて問題になったことがある。
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/03/h0320-1.html
これは中学生など特に未成年者で問題が報告されている。そのため未成年者に対して処方する場合は、特に理由がない限りはタミフルを避けて、イナビルを処方することが筆者は多い。採用などの関係でタミフルを選択する場合は、患者が一人にならないように様子を見てもらうなど説明を行なっていた方が無難だろう。
それ以外で薬を希望している→タミフル(オセルタミビル)
or イナビル(ラニナミビル)
一般的に成年後のリスクのない方に対しては、最も使用経験の多いタミフルを選択することが一般的ではないだろうか。私自身は、適応があり、患者自身も希望しているのであればタミフルを処方することが多い。また1回で済ませたいという患者に対しては、イナビルを選択する。
(参考文献)
Gao Y, Zhao Y, Liu M, et al. Antiviral Medications for Treatment of Nonsevere Influenza. JAMA Intern Med. 2025; doi:10.1001/jamainternmed.2024.7193
この記事を書いている人↓↓↓



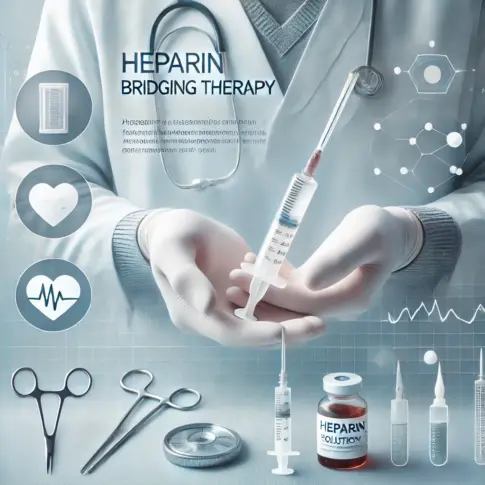
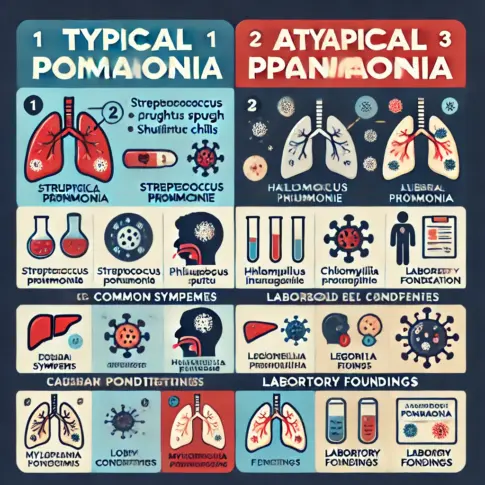


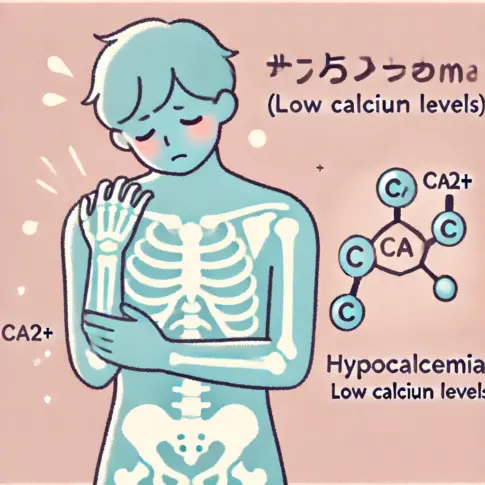

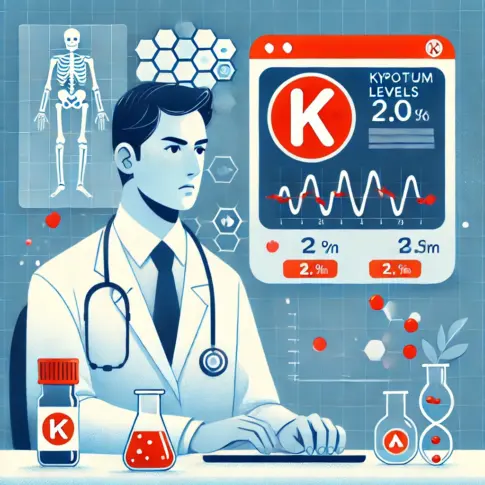

コメントを残す