末梢輸液の考え方・使い方
はじめに 輸液療法は入院患者に対して行われる頻度の高い治療である。輸液の適応となる病態を把握し、適切な輸液を選択することが必要である。入院自体が輸液の適応ではなく、過剰、不要な輸液に伴う合併症を避けることも肝要である。 ...
 未分類
未分類はじめに 輸液療法は入院患者に対して行われる頻度の高い治療である。輸液の適応となる病態を把握し、適切な輸液を選択することが必要である。入院自体が輸液の適応ではなく、過剰、不要な輸液に伴う合併症を避けることも肝要である。 ...
 未分類
未分類はじめに 酸塩基平衡異常は、重症患者の評価や治療方針の決定において極めて重要な情報源です。本記事では、「pH」「CO₂」「HCO₃⁻」「アニオンギャップ(AG)」といった基本所見から、代謝性・呼吸性のアシドーシス/アルカ...
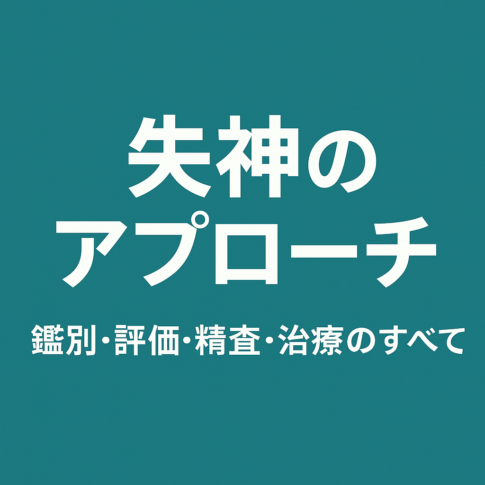 循環器
循環器失神(syncope)は突然の意識消失で始まる緊急性の高い主訴の一つです。一見良性に見えることもありますが、命に関わる重大な疾患の初発症状である場合も。今回は、失神のアプローチを、現場で迷わないための実践的フローとしてま...
 感染症
感染症肺炎診療の現状と課題 多くの研修医や専攻医の先生から、市中肺炎の診療には一定の自信を持ちながらも、いくつかの課題を感じているだろう。特に以下のような課題を答える専攻医の先生に出くわす。 ・抗菌薬の選択に不安がある ・細菌...
 common disease
common diseaseはじめに 毎年冬になると猛威を振るうインフルエンザ。多くの患者が発熱や咳などの症状を訴え、医療機関を受診する。特に高齢者や基礎疾患を持つ人にとっては、合併症を引き起こすリスクが高く、適切な治療が求められる。世界では300...
 common disease
common diseaseはじめに 高カルシウム血症は、血液検査で偶発的に発見される場合と、高カルシウム血症による症状で発見される場合がある。カルシウムは施設によってルーチンで測定することもあれば、ナトリウムやカリウムのようにルーチン測定しない場...
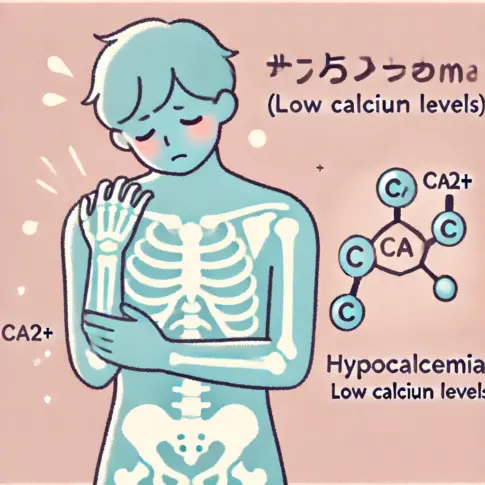 common disease
common diseaseはじめに 低カルシウム血症は、救急外来や病棟で遭遇することの多い電解質異常の一つである。特に重度の場合、テタニーや心電図異常を引き起こし、迅速な対応が求められる。本記事では、総合診療医の視点から低Ca血症の診断と治療の流...
 common disease
common diseaseはじめに 高カリウム血症は、救急外来や病棟で頻繁に遭遇する病態である。特に心電図変化を伴う場合は、迅速な対応が求められる。本記事では、総合診療医の視点から高Kの診断と治療の流れを解説し、実践的なマネジメントのポイントを示...
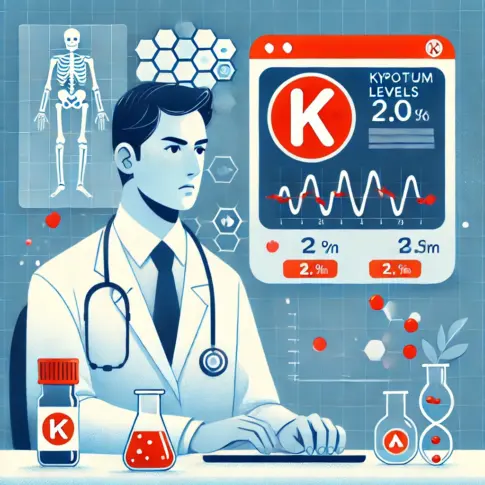 common disease
common diseaseはじめに 低カリウム血症は、様々な病態でみられる電解質異常の一つであり、重症化すると筋力低下、不整脈、呼吸筋麻痺などを引き起こすことがあります。特に重症低カリウム血症では、補正が難しく、治療初期にむしろK値が低下するケー...
 診断・臨床推論
診断・臨床推論はじめに 近年、人工知能(AI)は医療分野での応用が急速に進んでいる。特に、大型言語モデル(LLM)はその汎用性と高い診断推論能力で注目を集めている。だが、医師が実際にこれらのツールを診療で使用した場合、果たしてどの程度...